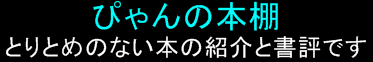
|
|
中山伊佐男著 『ルメイ・最後の空襲』 (2)(1)へもどる米軍資料に見る富山大空襲・空襲する側の論理が変わる日は来るか…… 米軍は、1940年の日本国勢調査をもとに、人口の多い180都市を空襲目標として選定していた。第20航空司令部が「中小都市空襲」作戦を立案する際、東京など3月10日〜6月15日の「大都市焼夷弾攻撃」で破壊された7市が外され、原爆投下対象都市の京都・広島・新潟・小倉も外される。さらに、航続距離不足から北緯39度以北の都市が外され、137都市が選定されていた。「戦争が終わっていなかったら、約80都市がさらに空襲で破壊されたかも知れないのである」 富山大空襲を命じたルメイ少将は、1945年1月、第20航空軍司令官に就任、3月10日の東京大空襲で低空焼夷爆撃に戦術を転換、軍事目標、戦闘員以外への武力行使を伴う「無差別爆撃」を作戦の柱としていく。本書には、その本音が垣間見える資料が紹介されている。 富山大空襲の「目標情報票」に「重要事項」として、郊外に重要な工場群があるが「密集地帯の方を攻撃することの方が、次のような諸結果をもたらすはず」と記載しているのである。企業の本社の破壊(中略)鉄道網の遮断などとともに「多くの労働者が市の中心部に住んでいる」と。これが「非戦闘員の殺戮命令」でなくてなんであろうか。(本書p.161) 実際、富山最大の軍需工場は目標範囲外とされているのだ。だが、著者は、声高に米軍を批判するのではなく、このようにも書いている。 日本陸海軍は国民政府の臨時首都、重慶に大規模な空襲を執拗に繰り返し、1940年には特に激しさを極めた。これこそが、(中略)ドイツ軍がスペインのゲルニカに行った爆撃と並んで、軍事施設と一般住宅を区別することなく爆撃する、いわゆる無差別絨毯爆撃の世界史的な始まりであった。(中略)世界各地で戦争は絶えず、20世紀を終わろうとする現在まで無差別爆撃は「性能」を上げ止むことがない。(本書p.134) ◇ 8月2日の攻撃では、富山を含む4都市合計で648機、焼夷弾は45241個・5127.9トンが使用された。16回の中小都市空襲の中で最大量(川崎コンビナートへの攻撃分を含めれば6252.4トン・他回は3000トン台)。米軍は「最大兵力」を出撃させているのだ。米軍資料には、防空砲火が無効(評者注:爆撃機の飛行高度まで届かない)とあり、日本の防空能力の著しい低下を把握していたらしい。日本に戦争継続が困難なことを米軍は把握していたはずなのにもかかわらず、なぜ最大兵力なのか――。真実の解明は難しいが、事実の暗合はある。資料から、攻撃の立案時点(7月20日〜24日)では実際より30%ほど少なく、1週間で増強されたとわかり、この間には、ポツダム宣言発表(7月26日)と日本による黙殺声明(28日)がある。著者は、増強との「因果関係がありはしまいか」と今後の課題を提示する。 もう一つの暗合は米国の新聞記事に示される。8月2日は「陸軍航空部隊の第38回記念日」で、ルメイ少将が「米国戦略空軍の参謀長になる」ため第20航空軍司令官を辞任する前の最後の作戦だった――著者は、「殺戮と破壊の大を祝う愚は戦争の常であり、日本側も同じような報道であったが、世界的な記録まで持ち出すこの臆面のなさには吐き気を催す…」と珍しく感情を言葉にしている。だが、一貫して冷静であろうと努める中山氏は同じ頁にこう記す。 ラジオなどで発表された「東海軍管区司令部発表」は次のような内容であった。『B29約70機は8月1日夜半、約2時間に亙り熊野灘方面より波状侵入し、富山付近を焼夷弾攻撃の語、遠州灘より脱去せり。(中略)本空襲により富山市各所に火災を生じたるも払暁までにおおむね鎮火せり』「鎮火せり」ではない、「焼尽せり」ではないか。言うのも馬鹿馬鹿しいが、新聞報道も被害を軽微に読み替えるばかりであった。(本書p.175) ◇ 評者は、1945年7月20日〜8月14日に、17都府県に50発の模擬原子爆弾(原爆と同型・同重量の1万ポンド通常爆弾)が投下された事実を本書で知った。威力検証のため投下予定都市を避けてデータを取り、原爆投下後もさらにデータ取りを続ける……。個々の命を見ない軍隊の冷徹さは恐ろしい。だが、戦争被害を未来に向け昇華させるには事実を見つめるしかない。国会図書館が購入した米軍資料から富山に関する部分(作戦任務報告書・空襲損害報告書・空襲目標情報)を整理した本書は、そうした学ぶべき過去を記した礎石の一つであり、今後の探求の一里塚でもある。 (2008年08月) 桂書房刊 本体2800円(税別) 1997年8月 |