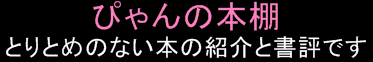
|
|
ギブソン著 『生態学的視覚論』
これは視覚についてのまったく新しい知覚理論を提唱した本です。
内容は、正直、よく解っていません。読んでる時は「うん、なるほど」とか「もっともだ!」とか、わかったつもりになるのですが、読み終るとよくわかっていないことがわかる。その原因はひとつは量が多いこと(本文で 300ページを越える)、もうひとつは独特な用語を厳密に使うことです。特に後者はちょっと時間がたつと意味の混乱が起きてしまって苦労します。まあ、メモでもとりながら読めばいいのでしょうが。では、誤解・曲解を恐れずすこし内容を紹介しましょう。 まず、知覚というのは人間の行動に関わるレベルの言語で語られるべきで、それは物理学・光学の言語や生理学の言語とは違うという主張がまずあります。だから視覚という知覚をよくあるカメラのモデルや網膜像で説明しようとしても駄目だ、それは問題自体が不適切だというわけです。そうした説明は生理学や光学に適切なものではあるが、レベルが違うのです。 そして環境と行動者の関わりとして、知覚(視覚)が扱われ理論化されていきます。 あるいは「アフォーダンス」というのを聞いたことがあるかもしれませんが、アフォーダンスは、このギブソンの出した概念です。この本でも一章をあてて論じています。 ごくごく簡単に言えば、アフォーダンスはどういうものか。たとえば、石なら石が、ある時には”金槌”として、別のある時には”ぶんちん”として、またある時には”椅子”として見える。それは石の方に違いがあるのじゃなく、見る人間の側に違いがあるからだ。つまり、人間が石を知覚するときに、石は”金槌”としての石をアフォードしたり、”ぶんちん””椅子”としての石をアフォードするのである。 このギブソンの考え方(生態学主義)は、『アクティブ・マインド』の中で佐伯胖氏が引用しているので(pp.10-12)、そこからアフォーダンスに関わる部分を引用しましょう。 たとえば、「すっぱい味」というものを考えてみよう。……「すっぱさ」というのは、別にお酢自体が人間と離れてもっている性質ではない。「すっぱい」というのはあくまで「人間にとって」という注釈がつくはずだ。……つまり、「すっぱさ」は人間が勝手に舌先で発生させているわけではなく、酢という実体によって引き起こされたものともいえるが、一方、酢にとってみれば、人間がいて、「味わってくれる」おかげで、自らの「すっぱい」性質が顕在化したのだ、といえる。こういうふうに「環境」というもの自体を、特定の生体が生活している生態系のなかで相互に依存しあって「立ち現れる」性質だと考えようというわけである。「環境」というものをこのように定義すると、ものごとの「知覚」というのは、環境のなかの事物の属性、すなわち、外界がその生活の活動を誘発したり方向付けたりする性質を、「直接に引き出している」ということになる。ギブソンはそのような「生体の活動を誘発し方向付ける性質」をアフォーダンスと名付けた。つまり、知覚とは、生体がその活動の流れのなかで外界から自らのアフォーダンスを直接引き出すこと、というわけである。……(以下略) (1990年09月) サイエンス社 1985刊 |
