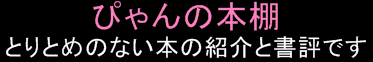
|
|
『ファン・ゴッホ書簡全集』 (全6巻)
印象派の画家ゴッホは、膨大な数の手紙をやりとりしました。
第1巻〜第5巻は、ゴッホからテオに送られた手紙を整理し出版したものの翻訳です(第6巻には、ゴッホから友人であったラッパルトやベルナールへの手紙、妹への手紙、テオからヴィンセントへの手紙が収められています)。兄の生活を支え続けていたテオは、ゴッホの死後、すぐに後を追うように死んでしまったので、実際の整理・出版にはテオの未亡人があたりました。 文面からは、ゴッホという人の心の内面や生活の内幕が赤裸々に書かれていて、いわゆる「芸術家の苦悩」だけでなく「生活者の苦悩」とも言うべきものを知ることができます。ゴッホという人は、人を愛したくて、愛を与えようとして、それゆえに誤解されてしまうことが多い。特に、いわゆる“良識のある人々”には、まず間違いなく誤解される。そんな彼の赤裸々な気持ちが弟にたいしてつづられています。 ゴッホは生活費のほとんど全てを弟テオに頼っていました。住むための金。食べるための金。着るための金。女を抱くための金。絵を書くための金。その全てを、弟からもらわねばなりませんでした。彼は自分には絵を描くことしかないと考えていましたから、弟に経済的に依存していること、自分で自分の生活費が稼げないことに罪悪感をもちながら、売れる絵を描いて生活できる様になるために、弟に金を送ってくれるよう手紙に書かねばならなかったのです。 それを書かねばならぬ時のヴィンセントの苦悩は手紙の端々から伝わってきます。 自分の出費が無駄使いではないこと、将来回収できるはずのものであること、売れる絵を書けるようになるために必要な金であることが、テオのお荷物になりたくないという言葉とともに記される。読んでいると、単なる芸術家の苦悩ではなく、人間として失格者扱いされまいとする人間の苦悩を味あわされます。。 ゴッホは、南仏のアルルで発作を起こします。この発作が実際のところどういうものであったのかは、今でも議論がありますが、サン・レミで精神病院に入ることになります。しかし、そこでの生活に耐えかね、オーヴェル・シュル・オワーズへと移って行きます。 この時期の書簡を読んでいると、ヴィンセントがずいぶんと枯れてしまったな、という印象を強く受けました、その理由が何なのかはよくわかりませんが。そして、弟のテオに経済的に依存しているということに対するうしろめたさだけは変わりが無い。そんな彼が、自分の描いている絵には大した価値がない、でも将来はお金を回収できるだろうと書いているのを読むと何だかものすごく痛々しく感じられます。 ただ、ゴッホが、自分で自分を苦しめていたとも言えると思います。 お金を無心しているテオに対する手紙と違って、友人への手紙には、ゴッホという画家のかたくなさ、頑固さ、激しさ(絵画・芸術に関しての)が露わになっています。特に、ラッパルトとの文通に、それがよく表れていました。たとえば、1885年 5月24日の手紙を全文を引用するとこうです。 親しいラッパルト 1885年 5月24日 自分の書いた手紙、しかも、真面目に芸術についての考えを書いた手紙が、この返事と共に送り返されてきたら、どんな気持がするのだろう。 フィンセントは、こと芸術に関して自分の意見に固執し、妥協することがなかったようだ。そのピュアさが、謙虚であった(らしい)芸術以外の面での性格とあいまって、ずいぶん多くの人に愛されては居たらしいが、同時にフィンセントという人に不幸(何が不幸か、わかりませんが……)をもたらしたのかもしれない。 (1990年06月) みすず書房 |
