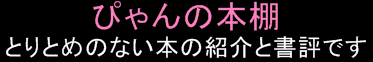
|
|
門野晴子著 『性教育 Q&A』本書は、1986年に門野氏が書いた『ザ・性教育Q&A』(青山館)を第1部として収録し、第2部(アメリカの子どもの現状と日本)では、1986年以後の状況の変化を視野に入れて「十代の親・性教育」「エイズ・ホームレス・ゲイ」「セクハラ・子どもの権利条約」の3つが収められている。 この本を読むと、門野氏の考え方・やり方に驚き反発する人がいるかもしれない。たとえば、門野氏は自分の娘と彼女の恋人とを自宅で同棲させている。これだけを読むと門野氏が何かとんでもないことをしたと感じる人の方が多いだろう。しかし、門野氏のこの選択には、氏の性への考え方と、青少年の性への考え方とが象徴的に表れているのだ。 氏は言う。 「娘と彼はその年(氏の娘が高1、彼は高3)の三学期から、わが家でいっしょに暮らしはじめました。わたしがふたりを認めたわけは、いけないと言えば、ウソをついて外で会うようになるでしょう。夜遅くまでうろついている高校生を見て、そうさせたくないと思ったのね。門野氏の基本的な考え方は、恋愛が個人の権利だということと、性はあくまで個人に属するものだということ。前者については娘の同棲を認めるところに表れている。後者については次のような記述を引用すれば氏の考え方を分かってもらえるだろうか。 「男も女も、マスターベーションは性の基本です」これを読むと「なんなんだぁ?!」と感じる人もいるだろう。それに対して氏はさらにこう説明している。 「(性欲を)ガマンすることはたいせつだけど、いつでもガマンしているとイライラしてきて、よくないわね。おうちでゆったりしているときや、眠りに入る前に、もちろんそういう欲求があるときに、自分で快感をえるのは、とてもステキなことでしょ。門野氏は恋愛と性を個人の権利として年齢にかかわらず認めている一方で、いや認めているからこそ、性に関わることについて正しい知識を得、正しく考えることを要求もしている。無条件に性の衝動に身を任すことをよしとしているのではないのだ。その結果として(当然のことなのだが)「性の神話」に対してはそれと闘う姿勢が一貫している。 そして、その姿勢の中でもっとも重視されているのが、「女も人間なんだということ」をきちんとわかること。これは特に男の子に対してはっきりと要求されている。氏の息子や娘の彼に対して門野氏は、このことをはっきりと理解することを求めている。 それを端的に表すのが次のふたつの記述だろう(カッコ内は筆者中)。 「私が息子と娘を育てた性教育に、一箇所だけ男女別のところがありました。それは『レイプ』についてです。息子には広義のレイプ(狭義のレイプ=強姦、広義のレイプ=女性の意志に反したことを暴力・脅迫などで強要されること)について語り続け、私とどなりあうことはいいのですが、妹をどらりつけたりなぐったりすることをダンコ禁じました(なぜならそれは広義のレイプだから)。その上、なにをやっても自分でオトシマエをつけるならかまわない、学校や警察に呼び出された場合はあなたの側につく。ただし、レイプをしたときはあなたを殺す!と言ったのです。」 本書の第1部は、それぞれのQ&Aの後に「親と教師へのメッセージ」がある。ここが実に面白い。子どもを”純真な存在”という枠組みに勝手に押しこもうとする親。子どもを守るという大義名分のもとに、子どもの権利を認めない教師。子どもの性を、”きれいごと”ですませようとする社会。そうしたものに対する苛立ちと怒りが行間に(言葉自体にも)表れている。 その中から一節を引用しよう。この一節で言われていることに対して教師・学校は考えなければならないだろう。 「ただ、どういう教育方針でも問題の起こりがちなそれは、共通している面があります。それは、はじめに入れものありき、ではないでしょうか。『勉強のよくできるいい子』とか『男らしい・女らしい』とか最初に枠組をつくってしまっていて、その中に子どもをはめこんでいく、という方針です。もちろん、この引用は門野氏が邪揄したものである。だから、そんなばかなことを求めてはいない、と反論する人も多いだろう。だが、ほんとうに違うだろうか? (1992年11月に書き2013年08月に直す) 朝日新聞社 1992 |
