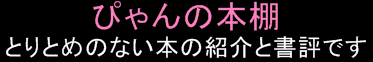
|
|
加藤尚武著 『環境倫理学のすすめ』
1992年に、本書を、こんな風に紹介したことがある。
◇ 本書は、タイトルにあるように、「環境倫理学」を紹介している。環境問題は倫理問題であり、技術問題ではないというのが本書の基本的枠組みである。そして、著者の言を信じれば、環境倫理学の主張の基本的な枠組みということになる。 本書が述べていることを、誤解を恐れずに私なりに要約してしまえば次のようになるだろう。 現在の文明の社会・経済活動は既に環境の許容限度を超えている。 このことは、現在の文明の基本的な価値観である「成長・進歩」が、もはや不可能になっていることを示す。 もし人類が生存を望むならば、「持続可能な社会」(「持続可能な開発」や「持続可能な成長」ではない)を実現しなくてはならない。 持続可能な社会」とは、「去年と同じ今年」ということであり、「成長・進歩」という価値観を捨てた社会である。 経済成長も人口の増加もない安定した社会がすなわち「持続可能な社会」なのだが、現実に、この価値観を受け入れるのは難しいだろう。従って、人類は滅びるということになると私は思う。 環境倫理学の3つの基本主張として著者が書いているのは「自然の生存権の問題」「世代間倫理の問題」「地球全体主義」である。それぞれが、政治的・法律的・経済的・哲学的に微妙な問題をはらんでいる。しかし、人類生存を最高目標とするならこれらを受け入れざるを得ないだろう、と思う。 さて、個人的に実にインパクトがあったのが、バイオエシックスと環境倫理学の間に対立があるという指摘である(本書7章)。 「環境倫理学(environmental ethics)では、地球上での人類の生存を可能な状態にしておくことが、いちばん重要な原理である。だから原則としては人工妊娠中絶の強制をしてもいいと主張する人も当然、でてくる。インドや中国で人工妊娠中絶を強制したとしても、西欧諸国が非難するのは間違いだということになる。 この問題には倫理学上の原理の一八〇度の対立が含まれている。個人の自己決定を原理とする立場と、全体の生存可能性を原理とする立場との対立である。」(本書 pp.78) そして 「世界全体では、先進国の一人当りの医療費と開発途上国の医療費は極端に違っている。先進国で一人が使う最大の医療費を開発途上国の最低限度の場合と比較したら、気が遠くなるほどのの違いになる。例えば日本では年間に一人で一億円の治療費の支給を保健から受ける人がいる。アフリカには百円の包帯を支給してもらえない子どもがいる。すると一人で百万人の治療費を使う人もいることになる。先進国の自己決定権は、ある意味では大変な贅沢でもある。」(本書 pp.86) (以下略) ◇ 当時の私は、自己決定権を重視する立場をとっていた。その一方で、環境教育を考えていて、両者の対立に途方に暮れていたようだ。略した部分には、本の紹介とは無関係な愚痴を書いている。 20年経っても、何ら解決されていないし、事態は悪くなっているように思う。ただ、個人的には、当時よりも見通しが良くなった気がしている。 世の中、たくさんの物差しがあって、それぞれで異なる評価が出る時、たった一つの物差しを選ぶのは良くない。あっちの物差しとこっちの物差しと、そっちの物差しと……、少なくとも、複数の物差しがあることを自覚して考える。 理想は捨てない。捨てないが、理想的でないからゼロ評価はしない。いくらかでもマシな状態を目指して、諦めずに、前を目指す。 そうやって生き延びていくしかないのだな。今は、それがわかった分だけ、見通しが良くなっている。 (1992年05月筆/2013年07月改) 丸善(丸善ライブラリー) 1991 |
