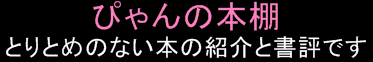
|
|
北村雄一著 『ありえない!?生物進化論』
進化の歴史を辿りながら、科学の本質を知る
世の中には、"トンデモない理論"がゾンビのように姿を現し続けており、そのことに心を痛めている科学者は多い。農獣医学部を卒業している著者もその思いを共有しているようで、読んでいると、科学の本質を読者に伝えたいという思いがこの本の背骨になっているのがよくわかった。 同時に、この本は、「生物進化」に興味をもつ読者を間違いなく楽しませてくれる。学者だと、科学とは何かを語る時に堅苦しくなりがちなのだが、ジャーナリスト&イラストレーターである北村氏は、進化に関する新しい成果(1990年代以降の新しい発見など)を紹介して読者を楽しませつつ、科学の本質を語るという難事業に挑戦し、それに成功しているのだ。 ◇ 第1章は、副題にもなっているクジラの進化がテーマで、クジラとカバが近縁だということが認められるまでの学問の流れが紹介されている。この過程で非常に重要な意味をもったのが、東工大の岡田典弘教授の開発した手法(SINE法)なのだが、この手法の紹介も要領を得ていてわかりやすい。同時に、科学の本質――データがどのように扱われ、どのようにより良い仮説に置き換わっていくか――が、クジラの進化という具体例と、それの準備となる"たとえ話"を使ってイメージしやすく語られていく。 第2章は、鳥の進化がテーマで、始祖鳥が鳥の祖先の座から落ちたり、その座に戻ったりした学問の流れを紹介しつつ、一歩進めた形で、科学の本質――系統関係を推論する場合にどのような証拠が利用でき、どのような証拠が利用できないかといった証拠の重要性の違い――を語っている。 第3章では、白亜紀末の大量絶滅がテーマ。白亜紀末の大量絶滅ではわからない人も、小惑星の衝突で恐竜が滅んだ事件といえばピンとくるだろう。この大量絶滅の原因についても複数の仮説があり、議論があり……。その中で、科学の本質――得られている証拠に基づくしかないので、証拠が少ないときには誤りもある――が語られる。 第4章では、科学の本質の一つである「仮説」がテーマ。これをどのように著者が語っていくかは、是非、手にとって読んで頂きたいと思う。 また、各章末には、「まとめ」というちょっと硬めの話があるのだが、それに続けて、コラムを置き、肩が凝らないよう配慮されている(コラムに取り上げられているのは、アフリカのヴィクトリア湖のシクリッドや三葉虫の呼吸など、これはこれで楽しめる)。 ◇ 残念だったところを挙げると、ダーウィンの進化論(自然選択説)を語っているp.94で、ダーウィンの時代には知られていなかった事例を並べているのが、誤解を誘発しそうで気になった。だが、すぐに気づくようなミスはp.33のイラスト(真核細胞のタンパク質なのに、転写と翻訳が同時進行する原核細胞の特徴で描かれている)だけで、チェックが行き届いている印象を受けた。それだけ、著者の思いの強い本なのだろう。「生物進化」に興味をもつ中高生を含め、誰にでも薦められる一冊である。 (2009年03月) ソフトバンククリエイティブ |
