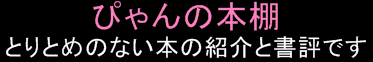
|
|
径書房編 『「びくろサンボ」絶版を考える』20年以上前(1991年)、こんな書き出しで本書を紹介したことがある。 「ちびくろサンボ」が絶版になったのが1988年の年末だから、すでに2年が経過した。新聞を初めとするメディアにこの問題が載ることもめっきりと少なくなっている。しかしメディアが扱わなくなったからといって、この問題が完全に解決したわけでもなければ、重要性が無くなったわけではない。それは単に、重要な問題が一時的にブームのように扱われ時とともに忘れられてしまうという日本に起こりがちな現象が起こったにすぎない。重要性は低くなるどころか、むしろ忘れられてしまうことによって高まっているとさえ言えるだろう。 2013年現在、こうした問題があったことさえ忘れられている気もしてしまう。だが、「ちびくろサンボ」絶版問題は、「ちびくろサンボ」という本の絶版だけの問題ではない。差別と表現・出版に関わる広く深い問題の一つに過ぎない。 20年前に読んだとき期待以上のものを得たと思った。径書房の編集部の人たち自身の「どうして? なんで? 」という素朴な疑問からスタートしているということが、本書をよい入門書にしたのだと思う。 1991年にこう書いている。 本書を読むと「ちびくろサンボ」絶版問題が如何に複雑で微妙な問題であるかがよくわかる。「ちびくろサンボ」絶版問題を考えるには、何が問題なのかをきちんと整理しないといけない。 まず「ちびくろサンボ」という作品をめぐる問題と「ちびくろサンボ」を絶版にすべきかどうかという問題は別問題だということがある。 前者はさらに「ちびくろサンボ」という作品が差別的であるか否かの問題と「ちびくろサンボ」を書いたバナマンという人が差別意識をもってこの作品を書いたのかという問題に分けられる。 後者の絶版にすべきかどうかの問題は、当然作品が差別的かどうかの判断に関わるのだが、それ以外に、児童向けの作品における改作の問題や差別反対運動への影響の問題がある。 それらを混乱したまま論じることは議論を不毛なものにするだけでなく、おそらくは害を流すことになるだろう。そういう意味で「ちびくろサンボ」絶版問題について考え、論じようと思うなら本書を読むことは必須であると思う。 ◇ 本書は、様々な人へのインタビューからなっているのだが、インタビューを受けた人の出身国や肌の色、性別、年齢は様々であり、当然、考え方も多様である。黒人のなかにも「ちびくろサンボ」が差別的だとする人と差別的ではないとする人がいる。どちらも納得できる意見であり、そのことが、差別と表現・出版の問題を考える難しさを現していると思う。 だから「ちびくろサンボ」絶版問題についての正解を求めると失望する。この本は、この問題への入口として読むべき本で、また読む価値のある本である。そして、差別と表現・出版について考える上での良い道標であり続けていると思う。 (1991年01月に書き2013年08月に直す) 径書房 1990 |
