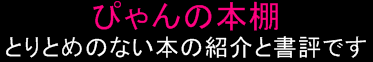
|
|
アーヴィング・ジャニス著 『リーダーが決断する時 Crucial Decisions』この本は、大統領や企業経営者など、大きな組織の責任者つまりリーダーが行う大きな決断について深く洞察しており、読む価値のあるものだと思う。ただ、タイトルを見て、特定にリーダーが特定の場面で行った決定的な決断についてのルポルタージュを期待すると裏切られる。素材としては登場するが、深く知ろうと思えば紹介されている資料に当たるしかない。 また、リーダーが決断する時のハウツゥ的なものを期待しても裏切られる。確かに、リーダーが“質の良い”決断をするために必要と思われるチェック項目は登場するが、すぐに使えるようなハウツゥにはなっていない。 この本の中で、著者は、「リーダーが行う重大な決断」を学問的に法則化しようとしている。本書は、ジャニスの学問的な挑戦の一里塚なのだ。 ◇ 本書にも明確に述べられていることだが、“質の悪い”決断をしても良い結果が得られることがある一方、“質の良い”決断をしても悪い結果に終わることもある。したがって、リーダーの決断を結果だけで評価することはできない。また、“絶対的に正しい”決断などありそうもない。しかし、“質の良い決断”と“質の悪い決断”を比べれば、前者の方が良い結果が多く悪い結果が少ないだろう。本書では、まずこの点が事例によって確認されていく。 その上で、“質の良い決断”と“質の悪い決断”の特徴が“仮説”としてリストアップされる。どれも、直感的には納得できるものだ。 そして、本書の中心をなすのは、リーダーを“質の悪い決断”に導くのはどういう条件なのかに関する検討である。ただし、著者は、あくまで検証すべき「仮説」であること、そして、根拠を提示する一方で、まだ検証が終わっているわけではないことを強調している。それは学者としては当然の姿勢であろうが、読んでいて、少なくとも私には、納得できるものが多かった。 たとえば、ボスが間違っていると思っても、後で報復されるのが怖くて言えないとか、仲間内からどう見られるかを気にするあまり、課題に対して“質の悪い”評価をしてしまうという分析がある。ほかにも、リーダー(たち)が、既に重大な課題に直面している時には、新たな課題を過小評価しがちであったり、新たな課題に対して“質の悪い”判断をしがちであるというのは、自分の個人的なことを考えても納得できよう。また、相手の振舞いの意味について判断しなければならない時、相手のことを快く思っていないと“質の悪い”判断になりがちだというのも、誰にも思い当たる節があるのではないだろうか。 ◇ 著者のアーヴィング・ジャニスは、「集団思考(groupthink)」に関する研究で知られている心理学者で、本書でも、集団思考を“質の悪い”決断に導く要因の一つとして取り上げている。 もちろん、集団で行う思考が批判されているのではない。ある状況に置かれた集団が陥りがちな思考パターンがあり、それを集団思考と名づけて、検討対象としているのである。 本書のp.71〜72より引用 かつて私は、政府諮問委員会の外交政策決定から生じた大失策に関する本を著したが、その中で、ある社会的制約が及ぼす微妙な影響をとりあげた。……。それは、団結力の強い上層部集団のメンバーにみられる“集団思考”の傾向である。集団の和を保とうとするメンバーの強い願望を背に、彼らは、議論の不一致や不和のもととなるものはいっさい退けようとする。この制約が優勢な場合は、構成メンバーはリーダーや集団の多数派がどんな政策上の立場をとったにしても、無意識に疑問を抑えこんでしまう。共通の集団意識のもとで、成功の予想を証拠だてる理屈づけをしようとし、そのために、自分たちの組織や国家が負けるはずがないという幻想を呼びおこす手段をとることが多い。このほか、意見の一致を求める(“集団思考症候群”と呼ばれる)兆候も現れる。 まるで、日本の集団について言っているような内容だが、この後に、イギリスの例が1つと、アメリカ合州国の例が4つ挙げられている。どうやら、日本では“日本的”と言われるものも、実は、ホモ・サピエンスに共通な特徴のようである。 内容とは直接関係はないが、アメリカ合衆国では、大統領(および側近)の政策会議等の記録(録音や文書)が、研究のために公開されているのだそうで、ちょっと驚いた。そちらを専門にしている人には周知のことなのだろうけれど……。長年、日本の政治を担ってきた自民党政権の会議の様子が録音されていたとも、それが公開されているとも聞いたことはないし、それどころか、記録を官僚が破棄するのを認めてきたわけで……。まあ、官僚が不都合な記録を破棄したがるのもホモ・サピエンス共通のようで、本書にも「官庁街で名高い“罰のがれ”の法則」という節がある。 本書では、“仮説”に基づく“提言”という位置付けになっているが、“質の悪い”決定を避け、“質の良い”決定を行うためのヒントが最終章に書かれている(第10章「危機に際しての効果的リーダーシップのあり方」)。読みながら、これを読んだら為になりそうな人の顔が頭に浮かんでならなかった(苦笑) (2010年09月/2013年08月修正) 日本実業出版社 1991 |