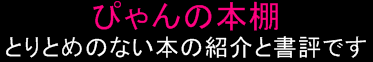
|
|
齋藤勝裕著 『毒と薬のひみつ』毒も薬も使い方しだい、この本も読み方しだい毒にも薬にもなりそうな本書には、膨大な数の物質が登場する。それらの多くには、毒としての側面と薬としての側面がある。著者の齋藤氏は、「はじめに」で、この両面性を強調する。そして、両面性を恐れず、きちんと向き合うためには正しい知識が重要だと書いている。 その通りだと評者も思う。だが、化学物質の毒性と薬効は難しい話で、正しい知識を得るのは容易ではない。 著者は分かりやすく伝えようと工夫をしている。たとえば、第1章の「1−1 毒とは人に害を与えるもの」から第11章の「11−9 うつ病は薬で治るか?」まで、94に話題が細かく分けられ、それぞれが見開きで完結するようになっている。また、正しい知識を無味乾燥に説明するのではなく、ミイラが薬として使われていた話を紹介し、毛染め液や甘味料・調味料といった身近な物質を扱い、クレオパトラのエピソードも書けば、最新の癌治療の研究やメラミンの事件も登場させる。 こうした工夫は、「本書を読まれた読者諸兄が、楽しみながら毒と薬に関する知識を身につけられるのが、著者のもっとも大きな喜びとするところ」と書いている齋藤氏の思いの結果だろう。 ◇ 評者は、著者の思いを素晴らしいと思うが、生物に関する内容のミスや不適切な説明が気になり、本書を手放しで褒めることはできない。 たとえば、「6−4 ビタミンとホルモンはなにが違う?」で、ビタミンとホルモンについて次のように書かれている。 ビタミンもホルモンも、生理的な機能は同じです。すなわち、両者とも「少量で生体機能を制御するもの」なのです。それでは両者の違いはなんでしょうか? 簡単です。人間が自分でつくりだせるものがホルモンであり、つくりだせないので食物から摂取せざるを得ないもの、それがビタミンなのです。(p.108より) これを読んで、評者は、首を傾げざるを得なかった。一般的な説明を『岩波生物学辞典』から引用する。 ビタミン: ホルモンが「特定の器官の活動に一定の変化を与える」というのは、言い換えれば、ホルモンが生体機能を"制御"しているということだ。ところが、ビタミンの説明に"制御"の意味は登場しない。ビタミンは生体機能に必須ではあっても"制御"とは言えないのだ。 さらに、「7−4 抗がん剤の開発」では、「DNAの異常増殖、それががんの本質です」という言い回しが出てくるのだが、DNAではなく細胞だろう。また、「6−8 不老長寿は存在する」では、「DNAが分裂再生」という表現が使われている。こちらは何度も登場するので、齋藤氏なりの意図があるのかもしれないが、一般的な「DNAの複製」を使わない理由に関する説明はない。率直に言って、本書の内容をどこまで信頼していいものか、少しばかり懐疑的になっていた。 ◇ 読了しても、懐疑的な気持ちが拭えなかった。だが、無責任に批判することはできないので、この文章を書く前に、眉唾に感じた部分をいくつか調べてみた。 「7−8 超分子の抗がん剤」には、薬剤を含まないリポソーム(脂質分子でできた小さな袋)が、がん治療に効果があるという話題が紹介されているのだが、リポソームそのものが抗がん作用をもつことに納得できなかったので調べてみると、実際に、ハイブリッド型リポソームの効果が学会に報告され、全国紙でも報道されていた。斎藤氏は、有機化学・物理化学・光化学・超分子化学を専門とする化学者なので、専門外の生物学的な内容や言い回しにミスや不適切な部分が、いくらか残ってしまったということらしい。 また、本書の10章・11章には、ローマ皇帝ネロが鉛中毒によって変貌したという話や、麦角菌と魔女裁判の関係、奈良の大仏を創建する際に起きた(とされている)水銀被害など、化学物質が歴史や社会に与えた影響が紹介されている。これらは、明確に証明されたものではないようだが、そうした仮説があるのは事実だった。たとえば、奈良の大仏を金メッキする際に用いられたアマルガム法では水銀蒸気が生じ、職人らに被害が出たらしい。読者が楽しく読めるような話題を選んだのだろうし、歴史的な話では、そもそも科学的な厳密さを求めるのが難しい。まあ、取り扱い注意、読み方次第ということだ。 ◇ 本書の「あとがき」には、次のように書かれている。 一方、覚醒剤が時の為政者によって意図的に使われる例もあります。第二次世界大戦における日本軍の特攻隊は、歴史の悲劇とも歴史の恥部ともいえることですが、ここで用いられたのが通称ヒロポンといわれる覚醒剤でした。 齋藤氏は、心の底から、化学物質が人間の役に立って欲しい、化学物質によって被害を受けることが無くなって欲しい、そう思っているのだろう。その思いは、正しい知識を得る手がかりになるが、ちょっとばかり注意が必要な本書に結実しているようだ。 (2009年03月) ソフトバンククリエイティブ |