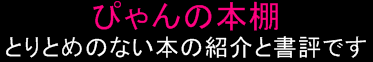
|
|
菅野盾樹著 『いじめ=〈学級〉の人間学』この本は、どんなに褒めても褒めすぎるということはないと思う。とにかくすごい本だ。〈いじめ〉をこんなに説得力をもって描いて見せてくれる本が他にあるだろうか。あの佐伯胖をして「すごい」と言わせただけのことはある。 まず、菅野氏は〈いじめ〉を解釈可能なものとして位置付ける。〈いじめ〉=表現。そこから分析を始める。 〈いじめ〉のもつ特質についての記述については一々紹介しない。それは是非読んで下さい。ただ、根本的なところだけ。誤解をおそれずに超・簡略化するとこうなる。 我々が社会や物事を分類する時に二項対立が使われる。が、「二項対立が第三の曖昧なカテゴリーによって媒介される」という点が重要。 「二項分割と曖昧さの産出とは一挙におこなわれるひとつの事態の二側面にすぎない」。 この観察から〈いじめ〉を見ると、「なぜ彼ら(『弱い子』や『鈍い子』)はいじめられるのだろうか。曖昧さを背負っているからだ」ということになる。 もちろん、これは〈いじめ〉を正当化しているのではない。〈いじめ〉という被害者にとって不当な現象が産まれてしまう理由の分析に焦点がある。 ここで重要なのは「秩序が曖昧さの創出をつうじてもたらされる」ということである。 「彼らに曖昧さが付与されることによって、集団の同一性が集団外のものに対立するかたちで確保されるのである」。彼らは「秩序の媒介役を強いられた」ということになる。 〈いじめ〉が起きる原因は、いじめる側がいじめられる人間を必要とするから。 この理不尽さを見出す分析は、議論のほんの出発点にすぎない。マスコミ等に報道された実例を解釈していくことを通して進められる議論は、日本文化の集団の創出の仕方という問題をも射程に入れる。そして〈いじめ〉の解決という方向へ視線を向けている。 読みながら、1ページに何度も頷く本というのは滅多にないがこの本はそういう本である。〈いじめ〉について考えたいと思うなら必読の本である。 1991年12月に書き2013年08月に直す) 新曜社 シリーズ・子どものこころとからだ 1986 |