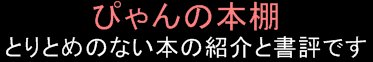
|
|
ディクソン著 『アサーティブネスのすすめ』「『アサーティブネス(積極的な自己主張)のすすめ』は、自分自身を、受身で人の言いなりになりやすい、あるいは攻撃的で人に喰ってかかる傾向がある、あるいは策士的で人を自分の都合のよいように操ろうとするところがある、と考えている女性のための本です。この本はどうすればアサーティブネスができるようになるかを説明します。また、基本的な行動様式にふれて、どのように変えるかを明らかにします。」(本書 pp.11「はじめに」より) この本の「はじめに」の冒頭部分からの引用に、この本がいかなる本であるかの全てが書かれています。この本は、アサーティブな人間に変るには、どのようにすればよいか、ということが実践的に書かれているのです。 「女性のため」とは書いてありますが、もちろん「男性にも役に立つ」本です。ただ、現代社会において男性と女性が置かれている状況の違いから「必要性が違っている」ということです。私は、日本文化の人間関係から考えると、女性と同じくらい男性にも必要なものであると思います。 「アサーティブネス(Assertiveness)」とは「積極的な自己主張」であるとされています。それは、現実生活の様々な場面において生じた問題に対して、「喰ってかかる攻撃的な」行動ではなく、また「踏みにじられても黙っている」のでもなく、「策士のようにもってまわった方法」で「相手の心に致命傷を与え」たり「自分の思うように人を操」ったりするのではなく、冷静にそれでいて積極的に対処する〈やり方〉です。別の言い方をすると人間関係の持ち方ということができるかもしれません。 「アサーティブネス」における焦点のひとつは「自分の責任で行動し選択し生活」するということです。ある意味ではこれが原点であると言えるかもしれません。「自分の責任で行動したり、選択したりしない」、つまり他人に選択を任せて行動したり生活することに「ノー」と言うところから「アサーティブネス」が始まるのです。 この本には、「アサーティブネス」を実行できるように自分を変えていく方法が、課題の形で書かれており、独りで(あるいはグループで)練習できるようになっています。その内容については書きませんが、実に実践的な内容です。誰でも、ちょっとした決心でできるだろうと思います(逆に言えば、このちょっとした決心をするのが大変なんでしょうが)。 著者の Dickson は「アサーティブな生き方の基本」という章(第5章)で、すべての人間が持つ「人間として当然の権利」について書いています。「この権利は生活態度の基礎となるもので」、「アサーティブな行動」の基礎ともなるものです。書かれている11の権利を簡単に引用しましょう。 1 私には、自分のニーズを言葉に言い表わし、自分で選んだ生活上の役割とは別に一人の人間として自分で物 本書の最後に「附 批判に答えて」が置かれています。「アサーティブネス」は、女性の生活の仕方を変えたために、英国において、様々な批判に晒されたようです。この章はそうした批判に対する Dickson の解答です。それらの中でここで紹介したいのは次の部分です。 「アサーティブネスを認めることは男性が男性であることの条件と衝突します。その条件というのはすべてのことに優れていること、弱さを隠すこと、強さを示すこと、誰よりも先に成功しなければ負けであることなど(こうした条件が男性が男性であることの条件、言い換えれば理想の男性の条件として機能している:引用者註)です。……(中略)……アサーティブネスの訓練は女性と男性に典型的に期待される行動の欠点を明らかにします。……(後略)」 この引用を次のように言い換えたらどうでしょうか。 アサーティブネスを認めることは教師が教師であることの条件と衝突します。その条件というのはいつでも正しいこと、弱さを隠すこと、強さを示すこと、秩序だった授業に成功しなければならないことなどです。……アサーティブネスの訓練は教師に典型的に期待される行動の欠点を明らかにします。…… また、 アサーティブネスを認めることは生徒が生徒であることの条件と衝突します。その条件というのはいつでも、自分の個性を隠すこと、規則や指示に従わなければならないことなどです。……アサーティブネスの訓練は生徒に典型的に期待される行動の欠点を明らかにします。…… これが当っているかどうかは、本書を読んだ上で、一人ひとりが判断してくれればいいのですが……。ひとつだけ気になるのが本書の表現です。日本語として硬い言い回しが多いような気がしました。 (1992年05月) 柘植書房 1991刊 (山本光子・訳) |