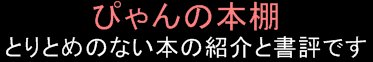
|
|
多田茂治著 『野十郎の炎』7月9日(2006年)に見に行った高島野十郎展で買った本で、野十郎の伝記です(あとがきによれば、旧版は2001年に出版されています)。私が絵を見るとき、基本的に、画家のことは頭から外します。もっと言えば、タイトル・作成年代も外して、言語を外すようにします。作品を解釈するのではなくて感じるために、そうしています(中学生のときから、そうやって見てます)。ですから、画家の生涯を(積極的に)知ろうとは思わないことがほとんどで、詳しく知る努力をしたのはゴッホくらいでしょう。 そんな私ですが、野十郎のことは知りたいと思った。 ま、理由はいろいろ挙げられますが、いちばん大きいのは、作品のもつ特異性で、今まで見てきた多くの画家のいろいろな作品と、本質的なところで違うと感じたこと。究極の写実と言うか、画家らしくない写実というか……、その原点・背景を知りたくなったんですね。カタログと共に、会場で買ってしまいました。 で、本の内容は……。 伝記ですから、彼の生涯が描かれるのですが、忘れられていた/再発見された画家というだけあって、明らかになっていない部分が多く、著者(明善中学で、野十郎の後輩にあたる)も「野十郎探索研究の一つの手がかりともなれば、明善後輩の私の役割は果たせる」と記しています。 それでも、野十郎が、“人間としての魅力”が豊かな人だったことは伝わってきました。印象的なエピソードを紹介します。 この伊藤本家邸内のアトリエに移って、野十郎はようやく心の平安を得て絵筆を執るようになったが、伊藤武はアトリエを訪ねたある日、そぼ降る雨に濡れる法隆寺の五重の塔を描いたかなり大きな絵(十二号)が眼にとまり、心を奪われた。まっすぐ降る雨の微細な線に包まれた五重の塔が、なにか神々しく見えたのだ。 金は必要なもの。でも、金が嫌い。 おそらく、金に支配されることを嫌ったんだろうと思いますが……、何とも、魅力的な人間です。 (2006年07月) 弦書房 2006 |