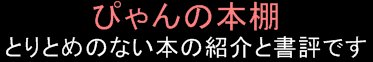
|
|
武村政春著 『一反木綿から始める生物学』妖怪に寄り道しながら生物学の道を歩く『ゲゲゲの鬼太郎』でお馴染みの妖怪「一反木綿」から始まる生物学とは、いったい、どんなものだろう? タイトルを見た時にまず私が感じたのは、その疑問だった。そして、一反木綿から始めて、猫娘やネズミ男、様々な妖怪を生物学の視点から分析する本かなぁ……。『鼻行類』(シュテュンプケ著・思索社刊)というジョークの先例もあるし……、それの妖怪版なら面白そうだ……。そんなことを予想していた。 だが、本書の内容は違う。真面目というか、生物学の内容を紹介することの方に主眼が置かれている。妖怪はあくまで入口あるいは脇道で、いろいろと寄り道をしながら、現代生物学の方へ話をもっていくのである。 ◇ たとえば第一章。一反木綿から始まる章では、一反木綿の起源から、一反木綿が空を飛ぶ話を経て、空を飛ぶ脊椎動物に話が行くかと思うと、一反木綿の飛び方から水中を泳ぐ下等動物の泳ぎ方に話が移る。 第二章では、魑魅魍魎から生物の世界に見られる多様性――生物の多様性だけでなく、細胞の多様性や分子の多様性――に話が展開し、再び妖怪の話に戻る。私が一番面白く感じたのは、この章の後半で語られる「ろくろ首の進化」だった。もちろん、生物学的な意味の進化ではないが、ろくろ首の祖先と思われる「飛頭蛮」が中国から日本に入り、鳥山石燕が「飛頭蛮」に「ろくろくび」と振り仮名を振り、その姿態を変えていくという「文化的な進化」は興味深かった。飛頭蛮と言えば、倉橋由美子氏の『首の飛ぶ女』(新潮文庫『倉橋由美子の怪奇掌篇』に収録)が思い浮かぶが、この作品もさらなる進化を作り出すのだろうか……。 さらに、第三章では遺伝子DNA、バイオテクノロジー、第四章では生態系、第五章では老化やがんの話題が、妖怪の話と絡めて、取り上げられていく。具体的には、「選択的スプライシング」や「キメラ」、「岡崎フラグメント」や「テロメア」など、分子生物学のかなり細かい点が紹介されている(著者の専門が分子生物学であるためだろう)。もちろん、こうした内容が書かれている部分には妖怪は登場しない。その前後に、寄り道するだけである。 全体を通じて話題の混ぜ方は、好みが分かれるだろう。きちんと順を追って説明を読みたい人には、話が切れるのが煩雑と感じるかもしれない。また、これも好みということになるが、妖怪の話と生物学の話の組合せに違和感をもつ人もいるかもしれない。妖怪か生物学か、どちらかをソコソコ知っていれば大丈夫と思うが、両方とも知らないとかえって読みづらいように思う。 残念だったのは、生物学の内容で小さなミスがいくつか見られたことである。96頁の「キラーT細胞」は前後の文脈に合致しないし、110頁の「クラゲの発光タンパク質」は正しくは「クラゲの蛍光タンパク質」(下村脩博士がノーベル賞を受賞したことで話題になった緑蛍光タンパク質)。124頁の生態系の説明や161頁の図26も適切とは言えない。校正のミスかもしれないが、もったいなかったと思う。 ◇ 調べてみると、武村氏には『ろくろ首の首はなぜ伸びるのか』(新潮社)という「妖怪の生物学」を扱った著作があり、妖怪ファンには有名らしい。妖怪の方に興味がある人は、この本と合わせて読むと楽しめるのではないかと思う。 (2009年03月) ソフトバンククリエイティブ |