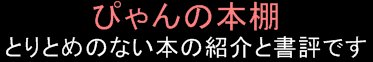
|
|
津田大介著 『仕事で差がつく すごいグーグル術』Googleをはじめ、Yahoo!やら、gooやら、infoseekやら。検索サイトを利用しても、探している情報がなかなか得られない。で、時間ばかり使って、探し当ててみれば、自分が持っている本からの引用だけだったり……。インターネットでの情報検索にはストレスを感じます。まあ、誰かがネット上に載せなければ検索にはかからないわけで、探す情報がそもそもネット上になければ仕方がない。それはいいのですけれど、無いなら無いで、効率よくやりたい。欲しい情報とは全然関係ないサイトが無駄にヒットするのは、時間を奪われるだけに非常にツライ……。 と言うわけで、タイトルに惹かれて買ってみました。その結果は? いろいろなテクニックが紹介されていて、実用書として元は取れます(でも、情報を検索して手に入るかどうかは別ですが・笑)。二つ三つ例を挙げると……。 言葉の意味を調べたいときは「とは」を付ける。 これは、言葉の意味を説明するときに、「〜とは」という言い回しが頻出することを利用するというアイデアで、うまくいきそうな気がしますよね。 学術的な情報を探すときは、サイトを限定して調べるコマンドの「site:」を使って「site:ac.jp」とする。 「ac.jp」は日本の大学を示すわけで、大学のサイトだけを対象に検索するというテクニック。「ed.jp」なら教育機関、「go.jp」なら政府機関。「site:amazon.co.jp」とすれば、アマゾンのサイト内をGoogleで検索できるなど応用が利きます。 この本の巻末には、Googleでの特殊構文集がリストになっていて、使いやすい点もお勧めです。 ところで、本書100頁に「グーグル八分ってなに?」というコラムがあります。これによると、Googleにはつぎのようなことがあるそうです。 グーグルは特定の企業からの要望や抗議に基づき、その企業を批判するページが自社の検索結果に表示されないような処理を行っている。これは日本では「グーグル八分」と呼ばれ、いくつかの企業を批判告発したサイトや、社会問題を扱うサイトがグーグルの判断(あるいは当該企業からの抗議)により、検索結果に出ないようになっているのだ。……(中略)……。グーグルの基本理念の一つに、「情報は技術のみで評価することで、ウェブの情報に『民主主義』を機能させる」ということがある。しかし、現実には人間の思惑で特定のサイトが削除されるという、恣意的な判断がなされているのだ。メディアリテラシーという意味で、Yahoo!とグーグルを併用することには大きな意味があると覚えておこう。 (2006年10月) 青春出版社 |