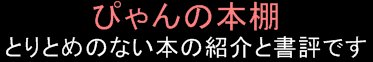
|
|
鶴見俊輔著 『文章心得帖』「この本は、昨年(1979年)三月から四月にかけて三度ほど現代風俗研究会の文章教室で話したときの記録で」鶴見氏が文章を書くときにどういう点に注意しているのかが書かれている。鶴見氏は「ただ、良い文章を書くようになりたいという理想」を目指す彼の取り組みかたの特色を述べている。 その内のいくつかを紹介する。 文章の理想の三方向は<誠実さ>・<明晰さ>・<わかりやすさ>。 誠実さとは、端的に言えば紋切型の表現を避け自分の言葉で書くこと。 明晰さとは、そこで使われている言葉の意味を問われた時にすぐに説明できること、つまり定義できること。 わかりやすいとは、特定の読者(それは筆者自身でもよい)にとってわかりやすいこと。 これ以外には、思いつき・裏づけ・うったえの三段階に文章のまとめ方を定式化していたり、文間文法の技巧を活用することを言ったり、目前の経験を解釈するカギとしての原体験の扱い方や動詞をたいせつにすることなどが記されていく。 また、書評について、次のようなことが述べられている。 書評には、「ほめる書評」と「けなす書評」がある。 書評の役割は何か。 その本がどういう本か、その特徴をパッととらえる。数行でとらえる その本が読むに値するかどうかを判断するだけの材料を与える その本を読んでない人にある種の情報を与える その本を要約するというハタラキ その本のおもしろいところは何か、つまらないところは何か その本の役割、効果 その本をどういう人に読んでもらいたいか その本のイメージをつくる 書評するさいの作法は何か。 否定する場合、根拠を示す その本に対して自分なりの独自の光をあてることが重要(立場を明確にするということかと思う) そして、悪い書評の特徴として、こんなことを挙げる。 情報量が少なく、学術用語を用いて誤魔化す 紋切型の表現を使う。流行語を使うと弱くなる(くだいた普通の言葉の方が強い) 書評するときには、鶴見さんの文章を参考にとは思う(とても足元にも及ばないが……)。 まず、どういう本であるかのイメージをつくる(おもしろいか、何が書いてあるか)。 誰が読めば意味・価値があるか、あるいは無いか。 どういう意味・価値があるか。 誰に向けて書評を書くか。 ほめるか、けなすか。 …… まあ、とにかく、「良い文章を書くようになりたいという理想を」共有するなら一読する価値のある本だと思います。 (1990年04月/1991年02月/2009年08月) 潮出版 文庫 1985 |