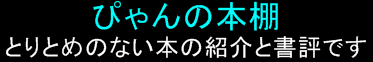
|
|
ナボコフ著 『ロリータ』ロリータは、12歳の少女と40過ぎの男性の間の性的関係を描いたポルノ小説ではなかった。卑猥な単語を並べ、直接的な描写をするのがポルノ小説だとすれば、性行為を匂わす表現はあっても、行為そのものを描いたところはない作品はポルノ小説ではない。ロリータは、12歳の少女に対する40過ぎの男性の恋を描いた恋愛小説でもなかった。確かに、主人公の心情は描かれているが、言い訳めいた語り口で述べられるのは、“ニンフェット”という幻想に対する心情であって、恋というには違和感が強い。 では何? ロリータ・コンプレックスという〈学術用語〉の源になり、ポルノ小説の世界にあるパターンを生み出した、この作品はいったい何なのか? 世の中を流れているイメージとは異なる印象を受けながら読み続け、そのまま終わってしまった。 訳者のあとがきを読み、腑に落ちたことも多いが、ロリータという作品はいったい何?という違和感は消えていない。訳者あとがきで、若島氏は、こんなことを書いている。 「あとがきでナボコフは、「『アメリカを発明する』という意図があったことを述べているが、これはけっして単なる大言壮語ではない。まさしくその言葉どおりに、ナボコフはいわば夢のアメリカをここで描き切ったのだとわたしは思う」 ロリータは、アメリカを発明した作品? どうやら、少女に対する性愛というテーマは外装なのらしい。 ◇ 若島氏によれば、ロリータ(原著は1955年刊行)は、いろいろと謎と議論の多い作品だそうである。そうした謎をめぐる学問的な議論は21世紀になっても続いていると、いくつかの話題が紹介されている。 たとえば、「現在、ナボコフ研究者の頭を悩ませ、意見が大きく二つに分かれている問題」として作品の中に出てくる数字をめぐる矛盾が紹介されている。書き間違いなのか、意図した矛盾なのか。筋を追う上ではどうでもよいような話なのだが、作品の細部までも理解したい人間にとっては重要な“小さな矛盾”をめぐる話は、短編サスペンスのようだ。 シャーロック・ホームズでは、作品に含まれる小さな矛盾を語ることがファンや研究者にとっての楽しみになっている。ロリータという“問題作”について論じて楽しむというとちょっと変な言い方になるが、若島氏のあとがきからは、研究者がロリータを論じて楽しんでいる様子がわかる。実際、ナボコフが作品に“仕込んだ謎”は数多あるようで、その謎を解く楽しさが、若島氏の語り口から伝わってくる。そんな中、あとがきの最後の方に、こんなふうに書かれている。 ハンバートは、彼の手記を、ロリータの死後に出版して欲しいと言い残す。(中略)それでは、手記が書き終えられてから、ロリータの運命はどうなったのか。それが気になる読者は、ぜひもう一度最初から再読してみていただきたい。それを知るだけでも、本書は再読する価値がある。(後略) ここまで書かれれば確かめたくなるのが人情というもの。ロリータの運命は気にならなかったけれども、ナボコフの仕込んだ謎には興味があったので、再読して確かめた……。 うん、ナボコフは凄い。ロリータという作品は、間違いなく研究者を魅了する謎の宝庫のようだ。 (2012年01月) 若島正訳 新潮社 2005/原著1955 |