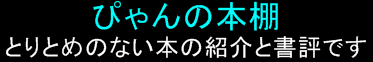
|
|
中西準子著 『飲み水が危ない』本書で中西氏が書いていることで、特に重要だと思うのは、リスクをリスクだけで論じるのではなく、リスクと効用との比(リスク/効用)で考えることの必要性である。重要性ではなく必要性であることがポイント。この〈必要性〉が分かりやすく説明されている。 「私たちは長い間、発ガン性物質というのはゼロであった方がいい、だからゼロにしろという要求できたのです。しかし、それだけではこういう理論に負けてしまうのです。 うまく反論できないのは、リスクをリスクだけで論じているからだ、リスク/効用という概念で考えていくことで、反論していくことができるということを中西氏は述べてます。 これは、運動家(の一部)にとっては、後退あるいは日和見ととられることもあるようですが、リスク/効用の比で考えることが文明社会によって作られた環境――水道とか、保存料、薬剤など――を考える場合には絶対に必要なのです。このことを理解しなくては、環境運動・環境教育ともに無意味(非生産的・非現実的)なものになってしまうでしょう(同様の考え方を安全規準に適用しているものとして、武谷三男編『安全性の考え方』岩波新書がある)。 さらに、水道水の現実(水道水が安全であるというのが嘘であること)や水道行政のおかしさ(安全のための規準の矛盾や、浄化の方法の非合理性)といった、現実についての重要な情報も書かれており、水道や水で環境教育をする場合には必読の書であろう。 といったことを20年前に紹介しましたが、個々の事実は変わっても、分析の視点としてリスク/効用の比が必要なことに変わりはありません。ま、20年前よりも、普通に耳にするようにはなりましたが。 (1991年11月に書き2013年08月に直す) 岩波書店 岩波ブックレットNo.144 |