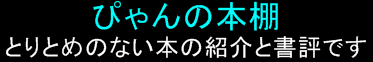
|
|
中冨信夫著 『宇宙はここまでわかった』著者紹介には、博士号(工学)をもち、宇宙科学・工学の評論などで活躍しているとある。その中冨氏の『宇宙はここまでわかった』は、1992年時点での最新の成果を視野にいれた、宇宙特に太陽系に関する教養書である(参考文献は1992年まで引用がある)。わかりやすい。これが本書の特徴の第一である。 章立ては有りがちな構成であるし、正確さにこだわる結果として専門用語・固有名詞が頻出し煩わしい印象を与えるという欠点もある。しかし、この本のわかりやすさは、そうした欠点を十分に埋めるに値するものである。 わかりやすさの例を「宇宙汚染(Space Debris)」の章に見てみよう(個人的には「Space Debris・スペースデブリ」を「宇宙汚染」と訳すのは適切ではないと思う。素直に「宇宙ゴミ」で良かったのではなかろうか)。 この章では、地球の周囲を回っている「スペースデブリ」即ち不要な人工物体(寿命の尽きた人工衛星や宇宙船の破片など)が扱われている。「スペースデブリ」はなんとすでに350万個(直径1ミリ以上)も存在しているというのだ。宇宙船や人工衛星が衝突しても不思議はなく、実際地球を約450周する間に889回の衝突が起きたという観測例がある。 「秒速8キロ」(!)で地球の周囲を回っている「スペースデブリ」が宇宙船などに衝突すれば様々な障害が発生する。だが、仮に直径1センチの「スペースデブリ」が宇宙船に衝突したら、その時の衝撃は……と言われてもピンと来ない。そこで中冨氏は「衝撃は、自重2トンの乗用車が時速51.6kmで衝突したのに相当する」と書く。この身近なものに置き換える方法そのものは目新しいものではない。中冨氏の素晴らしさはこの方法を本書で一貫して用いる点にある。新鮮な話題について専門的な説明がありさらに身近な事例に置き換えての説明がある。このパターンで1冊を通しているために、最初から最後まで非常に読みやすいものになっているのである。 2章以降では、太陽系の惑星を火星、金星、地球、月、水星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星(2009年の今は準惑星ですが)を順に扱い、次いで小惑星、彗星・隕石、さらに太陽、そして最終章で銀河系と系外銀河を扱っている。どの章にも最新(1992年での)の知見が分かりやすく書かれており、天文の好きな人にはお薦めの本である。 (1993年06月/2009年09月) 主婦と生活社 1992 |