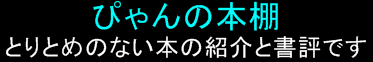
|
|
スポーツグラフィックナンバー編 『スーパーグラフ 清原和博VS桑田真澄』この本は、清原和博と桑田真澄の二人が新人であった1986年のシーズンが終わった後に出版された。それから7年間たって読んでみると、二人がいかに期待されてプロ野球界に入ったかがわかる。しかし、記録(数字)という形で述べられているものを読むと、彼らに対する(特に清原に対する)期待が過大なものであったこともわかる。 「1シーズン65ホーマー(2試合に1本)、1試合5ホーマー、五年連続三冠王、打率4割、生涯ホーマー1000本……そんな期待を抱かせる怪物なのだ。」 7年間の現実は、シーズン40本塁打すらなく、三冠王どころかタイトルも未だ獲得していない。 こう書いたからと言って、別に清原という選手を卑しめているのではない。スポーツジャーナリズムの新人選手に対する言葉を問題にしたいのである。 日本のマスコミは有望な新人選手が現われると、その選手を別格な存在に祭り上げたがるようだ。しかし、それは「こうであればいいな」という勝手な期待であり、プロ野球という日本で最も高いレベルの野球におけるその選手の力を評価したものではない。 「新人から別格の活躍をしスーパースターとなって最高記録を残し引退していく」というマスコミにとって都合のよい予定調和の物語を創ろうしているだけなのだ。例えば、前述の数字にしても、そこには王貞治というスーパースターの存在が意識されているわけだが、王と清原の能力は別にしても、球場の大きさ(後楽園両翼86メートルに対し西武ライオンズ球場94メートル、後に100メートル)やバット(圧縮バットは現在使用禁止)の違いがある。 そうした点はタブー視されて(王の記録が汚れるのかな?)触れられることなく、ただ数字だけが語られる。 来年プロ入りする松井秀喜に対する視線もきっと物語を創ろうとする勝手な視線になるのだろう。そして、勝手な期待が裏切られると、批判する。結局のところ、日本のスポーツジャーナリズムは、まだスポーツを「記憶」として語る言葉をもっていないのだろう。スポーツを勝ち負けや「記録」として語ることしかできないのだ。 このように書いてから時が流れ、2008年シーズン終了後、清原選手と桑田投手は、ともに現役を引退した。その間には、清原選手のFA移籍や桑田投手の自由契約・MLB挑戦など、さまざまな出来事があった。 また、予想通り“物語”の主人公にされた松井選手は、ヤンキースへのFA移籍を選び、世の中に衝撃を与えた。 松井選手は、“周囲が期待する物語”の主人公であることよりも、“自分の物語”を選んだのだろう。想像力を逞しくすれば、その決断の裏に、読売ジャイアンツという球団の清原に対する扱い――かなり清原に対する無礼な扱いがあったようだ――が影響してるとも思える……。 プロ入り時からの清原ファンの一人は、大阪ドームでの清原選手の引退試合と挨拶をTVで見て、「彼が野球を恨んだまま引退しなくて済んでよかった。亡き仰木監督に感謝したい」と言っていた。私も同感だ。 印象的な場面の記憶を残してくれた二人が、監督として対決する――“周囲が期待する物語”としてではなく“二人の物語”として――日が来れば、素晴らしいことだと思う。 (1992年11月/2009年07月) 文芸春秋社 ビジュアル文庫 1987刊 |