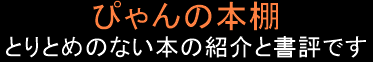
|
|
フルッサール著 『DNAと新しい医療』
この本は、生命と医療を物質という観点から理解しようという試みの成果です。
生命を(特に人間の生命を)物質という観点から扱うことに抵抗を感じる人もいるかもしれません。しかし、事実として生命は「物質」なのです(“人間の生命”の全てが物質だというのではありませんが)。物質は物質の法則に支配されます。それはある意味では平等であり、ある意味では残酷です。 生命を支配する物質は、究極的には「遺伝子」です。ひとりひとりの人間の運命のある部分、つまり“物質でできた機械”としての人間の運命は、「遺伝子」によって決定されています。数多くある病気のうちのあるものは、「遺伝子」によって、人間が誕生した瞬間に運命づけられてしまうのです。 「遺伝子」の本体がDNAです。そしてDNAを研究対象としているのが分子生物学です。 この本は分子生物学の現状を概観し、その後で医療における分子生物学の現状を描いています。こう書くと、分子生物学によって難病が治るようになったというような明るい話題を期待されてしまうかもしれない。が、残念ながら、現状はそこまでいっていません。分子生物学の発展によって、「診断」は可能になったけれども「治療」する方法が開発されていない疾患が多いのです。 こうしたテーマについて、心臓病やがん、アレルギー・アルツハイマー病などがとりあげられています。 この本の最後では永遠のデーマである「環境と遺伝」が扱われています。実際、病気の多くは「遺伝子」にのみ支配されるのではなく、「環境」の影響もうけます。その度合いは病気の種類によって様々です。「遺伝か環境か」というような単純な話ではないのです。この問題に対して、どのような態度が妥当なのか、有意義な示唆が得られると思います。 遺伝子によってなる病気が決まっているですよ、実際に。なんか残酷なような気もするけど……でも、(いろんな遺伝子があるということは)人間全体という視点にたてば良いことなんでしょうね。でも、人間は個人の尊厳という名のもとにひとりひとりを等価値だと思ってるから……難しい。 こんな風に書いてから15年。 分子生物学の進歩は、DNAだけが生命を支配しているのではないことを明らかにしてきました。同時に、DNAを利用した治療はなかなか進展していません。今後、どこまで実用できるようになるのでしょうか……。 (1993年01月に書く/2009年07月に直す) NHK出版 1992刊(原著1991) |