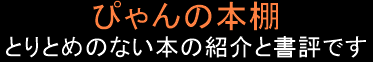
|
|
福澤一吉著 『科学的に説明する技術 その仮説は本当に正しいか』
何かを科学的に説明する技術を知りたい。そんな気持ちをもつ人が、How-to本のつもりでページを開くと、驚くことになるだろう。実は、この本は「科学」がどのようなものかを説明している本なのだ。
著者は、「はじめに」にこう書く。 本書は科学的成果を出すまでに科学者はどんな思考、推論をし、科学的営みを実践しているのかを考えるものです。そのときに、科学的思考、推論をベタなままとらえるのではなく、それをちょっと突き放しながらながめることを目指しています。 目指す地点を明確にすることは重要だが、それで達成が容易になるわけではない。たとえば登頂を目指す場合、チョモランマ(エベレスト)か、マッキンレーか、富士山か、高尾山か……で、その困難さは大きく異なる。著者が目指したのは、登山でいえば8000m級の高みだと私は思う。 というのは、「科学的営み」を検討する場合、科学の成果を事例とするので、科学的内容を理解し、読者が理解できるように書く必要がある上に、哲学や論理学で使われる用語や理論が必要になり(科学とは何かを研究しているのは、科学ではなく、科学論や科学史・科学哲学である)、それらを理解し、読者に理解できるように書かなくてはならない。著者は、科学と哲学という、二重の重荷を背負うのだ。 福澤氏は、この困難な目標に向けて、さまざまな工夫を重ねている。 まず、話題を小さく分け、順序立てて、全体を理解できるよう配列している。各話題は、見開きごとに完結させ、片方は文章で解説するが、もう一方は、要点の図解やイラストを載せ、(架空の)対話やたとえ話を使い……、理解する手掛かりとする。事例も、相対性理論のような内容を理解するのに苦労するものではなく、著者の専門(認知神経心理学)を反映しているのだろう、脳科学や心理学の話題で親しみやすい。 たとえば、第2章の「日常議論から科学的な議論へ」では、まず、「日本人はなぜ英語をうまく話せないのか」という日常議論を扱い、科学的な議論との違いを説明する。そして、「科学とは何か」について、「科学とは、1.観察したこと(事象、現象、対象など)を、2.論理的に、3.実証的に、4.説明すること」と定義し、1〜4について、60ページ以上を使って丁寧に述べていく。 評者が面白く感じたものの一つが、「観察」に関する部分で、「観察語」と「理論語」という科学哲学の用語、そして「理論的」とはどういうことかが説明されるところだった。ここでは、心理学の卒論を書こうとする学生と指導の教員が登場する。この学生は、「校則を生徒に守らせようとすると、生徒の個性が発達しない」ということをテーマにしようとして、教員から、個性とは何だと質される。日常議論なら質されることはない語でも、科学となると別。結局、学生の考える個性は「その人なりの特徴であり、ほかの人と違っている部分で、かつほかから大切にされる部分」だということになり、話が進む。少し長いが引用してみよう(太字は原文)。 教員: これだけでも「理論的」という言葉のイメージが変わるのではないだろうか。だが、「観察語」・「理論語」を知っている人には丁寧過ぎるだろう。この本全体を通じて、こうした丁寧な説明が続くので、悪く言えば"情報密度"が低いのだが、想定している読者に対しては、この丁寧さが必要だったと思う。 これ以外にも、「懐疑的思考をどこかで止める」では、懐疑的であることは、科学的であることの一部をなすが、懐疑を途中で止めないと「科学的営み」が成立しないことが語られていたり、「仮説演繹法は推論上の誤りを含んでいる」や「説明したいならその答えを先に用意せよ?」など、一見すると"トンデモな"表題をつけた上で、科学のもつ特徴と限界がきちんと説明されており、「科学とは?」を考えたい読者には楽しめる本だろう。 ◇ 実のところ、読み終わった時に残念だと感じた。楽しめたし、勉強にもなったが、充実した内容と本の題名が合致していない。帯の「どうすれば、あなたの主張は通るのか」という文句は、さらに中身と離れている。この題名と帯では、「科学哲学」に興味をもつ人は手に取らないだろうし、How-toを期待して手に取った人は楽しめないだろう……。それが残念に思った理由だ。内容が良いだけに、この看板の掛違いは本が可哀想だった。 (2008年12月に書く) ソフトバンククリエイティブ 2007年 |