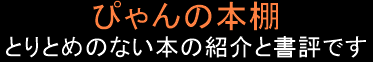
|
|
平野啓一郎著 『私とは何か』
この本の核心は、サブタイトルにもなっているが、新しい現実を構成する〈分人〉という語である。〈分人〉は、平野氏が長編小説『ドーン』に登場させた造語だが、この語を使うだけで「世界の見え方は一変する」(p.3)ことになる。読む前には、世界の見え方が一変するなんて大袈裟だと感じるかもしれないが、この本を読んだ後には〈分人〉を使うと世界の見え方が一変することを実感する。
なぜ実感するのか。それは、〈分人〉が「日々の生活の中で、恐らくは、多くの人が漠然と感じているはずのことに、簡便な呼び名を与え」(p.176)るものだからだ。人間は、何となく感じているが、うまく言えないことを数多く抱えている。その時に、ピッタリした名前がつくとスッキリし、うまく説明できるようになる。 本書は、抽象的な議論で進む学術書とは異なり、エピソードを使って書かれていく。これは、読みやすいだけでなく、〈分人〉を使うと世界の見え方が変わることを実感しやすくしているように思う。 ◇ サブタイトルにあるように、〈分人〉は〈個人〉と対比されている。個人は、英語では〈individual=分けられないもの〉であるが、平野氏によると、西洋で確立した人工的な概念であり、「『個人』という単位自体が確立されたのは、ようやく近代になってからであり、『個人主義』という思想の誕生は、更に十九世紀の半ばに差し掛かってからのことだった」(p.186-187)のだそうだ。西洋社会は、社会的・時代的な必要に応じるために、〈individual=分けられないもの〉を一人の人間を指す語にしたということらしい(本書はわかりやすさが優先されているため、西洋が〈個人〉を生み出した背景の分析はごくわずかに紹介されるに留まっている)。 近代社会から現代社会に変わる中、〈個人〉という語/概念の賞味期限が切れてしまったと言ってよいのだろう。もちろん、有用性がゼロになるわけではないが、世界を理解し生きていく際の〈単位〉としては力不足になったのは間違いない。そのことが本書を読むとよく理解できる。 平野氏には、〈個人〉を単位として世界を見る常識を問い直し、新たな思想を必要とする時代になっているのだという認識がある。〈個人〉が〈individual=分けられないもの〉だからこそ、問い直すために、一人の人間を〈dividual=分けられるもの〉としてみることが必要だと、少なくとも、そのような視点から分析し直すことが必要だという指摘は、その通りだと思う(私は、目から鱗を落としてもらったような気がした)。 ◇ 〈分人〉という造語に強い違和感を感じる人もいるだろう。平野氏自身、「分人という用語は、その分析のための道具にすぎない」(p.8)とし、「従来のキャラとか仮面といった言葉で十分なんじゃないかという指摘を何度か受けた」(p.25)にもかかわらず、〈分人〉という造語を採用する。それには、平野氏自身も書いているが、明確な理由がある。キャラや仮面の語は「従来の」語なので、従来の世界の見方(価値観)から自由になれないのだ。この弱点は、従来の世界の見方を問い直す際には致命的になる。 〈分人〉を使って、従来の考え方や世界の見方を問い直すと、どんな新しい世界が姿を現すのか? 本書の魅力は、この新しい姿を提示しているところだが、短い文章では紹介できない。是非、読んで実感して欲しいと思う。特に、「他人が理解できない」と感じている人(困っている人)や「他人に理解してもらえない」と感じている人(困っている人)には、〈分人〉は有用な道具になるだろうと思う。 (2015年7月記) 講談社(現代新書) 2012年 |