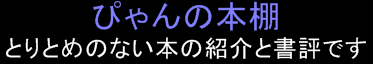
|
|
媨嶈惔岶丒忋栰捈庽挊丂亀帇揰亁
丂乽帇揰乿偲偄偆尵梩偼傛偔巊傢傟傞丅偦偟偰丄偦偺巊傢傟曽偼懡條偱偁傞丅
丂偙偺杮偼丄偙偺乽帇揰乿偵擇偮偺懁柺偐傜傾僾儘乕僠偟偰偄傞丅偦傟偼丄乽帇揰乿偺傕偮懡悢偺懁柺偺偆偪偺擇偮偵傾僾儘乕僠偟偰偄傞偲尵偄姺偊傞偙偲傕偱偒傞偐傕偟傟側偄丅 丂埖傢傟偰偄傞偺偼丄恖娫偑壗偐傪傢偐傞帪偵乽帇揰乿偑偳偺傛偆側栶妱傪壥偨偡偺偐丠 偲偄偆栤戣偱偁傞丅 丂偙偺栤戣偵偮偄偰擇偮偺懁柺乗乗嘥晹偱偼乽抦妎乮摿偵帇抦妎乯乿偺懁柺丄嘦晹偱偼乽懠幰棟夝乮暥妛嶌昳偺棟夝乯乿偺懁柺乗乗偐傜傾僾儘乕僠偡傞丅偮傑傝丄乽帇揰乿偼乽抦妎乿偵偍偄偰偳傫側栶妱傪壥偨偟偰偄傞偺偐丠 偲偄偆栤戣偲乽帇揰乿偑乽懠幰棟夝乮摿偵暥妛嶌昳偺棟夝乯乿偵偍偄偰壥偨偡栶妱偼丠 偲偄偆栤戣偺傆偨偮傪峫偊傛偆偲偟偰偄傞偺偱偁傞乮慜幰偺栤戣傪忋栰巵偑丄屻幰傪媨嶈巵偑榑偠偰偄傞乯丅 丂嘥晹偺乽帇揰偺偟偔傒乿偱偼丄乽帇揰乿傪乽傕偭傁傜丆偳偙偐傜尒偰偄傞偐偲偄偆偲偒偺乬偳偙乭傪偝偡応崌乿偵尷偭偰巊偆丅偦偟偰変乆恖娫偺抦妎偑丄偁傞屌掕偟偨帇揰偐傜偺僗僫僢僾幨恀偺傛偆側傕偺乮偙偆偟偨峫偊曽傪乽僗僫僢僾僔儑僢僩丒儌僨儖乿偲屇傫偱偄傞乯偱偼側偄偙偲偑榑偠傜傟偰備偔丅 丂恖娫偼乽帇揰乿傪摦偐偟偮偮尒偰偄傞乮帇抦妎乯偺偱偁傞乮抦妎偺乽棳摦儌僨儖乿偲屇傇乯丅偙偺峫偊曽偺婎偵偼James J. Gibson 偺帇妎榑乮亀惗懺妛揑帇妎榑亁嶲徠乯偑偁傞傛偆偱偡丅棟榑揑側撪梕傪埖偭偰偼偄偰傕嬶懱揑側帠椺乗乗幚尡忬嫷傗嶖帇偺椺乗乗傕徯夘偝傟偰偄偰敾傝傗偡偄偲巚偄傑偡丅 丂嘥晹偺嵟屻偱埖傢傟傞乽帇揰偦偺傕偺乮偮傑傝帺暘帺恎乯偵偮偄偰偺忣曬乿偵娭傢傞栤戣傕側偐側偐嫽枴怺偄丅恖偑奜晹偐傜忣曬傪庴偗庢傞帪丄偦偺忣曬偼扨偵偦偺奜晹偵偮偄偰偺忣曬傪傕偨傜偡偩偗偱偼側偔丄偦偺恖帺恎偑偳偆偄偆乽帇揰乿偵偁傞偺偐偺忣曬傪傕傕偨傜偡偲偄偆偙偲偵栤戣偺億僀儞僩偑偁傞丅偛偔娙扨偵尵偭偰偟傑偊偽丄恖娫偼帺暘乮帇揰乯偑摦偔偙偲偵偲傕側偆乽尒偊乿偺曄壔偐傜乽懳徾傗娐嫬偵懳偡傞帺暘偺埵抲偩偗乿偱偼側偔乽帺暘偑偳偙偵岦偐偭偰偳偺傛偆側摦偒曽傪偟偰偄傞偐傪傕乿抦傞偙偲偑偱偒傞偲偄偆偙偲偱偡丅偦偟偰偙偺媍榑傪傆傑偊偰悢妛偵偍偗傞乽扨埵偺曄姺乿傗暔棟偺乽塣摦乿偺棟夝乮岆夝乯偑榑偠傜傟偰偄傞丅 丂嘦晹偺乽帇揰偺摥偒乿偼乽暥妛嶌昳偺棟夝乿偲乽帇揰乿偺娭學偑埖傢傟偰偄傑偡丅偨偩丄乽暥妛嶌昳偺棟夝乿傪撈棫偺傕偺偲偟偰偱偼側偔丄乽懠幰棟夝乿偺傂偲偮偺働乕僗偲偟偰埵抲晅偗偰偄傞偙偲偼拲堄偡傋偒偐傕偟傟側偄丅挊幰偼乽暥妛嶌昳偺棟夝乿偵尷掕偟偨媍榑傛傝傕堦斒揑側媍榑傪乮嵟廔揑側乯栚揑偲偟偰偄傞丅 丂傑偢乽惣嫿晲旻偺帇揰榑乿偑娙扨偵徯夘偝傟偰偄傞丅偦偟偰亙忣宨棟夝亜偲亙怱忣棟夝亜傪乮媍榑偺搒崌忋姼偊偰乯嬫暿偟丄師偺栤傪偨偰傞丅 乽帇揰傪愝掕偟偨傝丆堏摦偟偨傝偡傞偙偲偼忣宨棟夝傪怺傔傞偩傠偆偐丏怺傔傞偲偡傟偽偦偺攚屻偵偼偳偺傛偆側怱棟揑夁掱偑懚嵼偡傞偺偐丏乿 丂偙偺擇偮偺栤偑嘦晹慡懱傪捠偠偰榑偠傜傟偰偄偔丅偦偟偰偦偺拞偱乽亙尒偊亜愭峴愴棯偺桪埵惈乿偑庡挘偝傟偰偄傞丅乽亙尒偊亜愭峴愴棯乿偲偄偆偺偑嘦晹偺乭攧傝乭偺傛偆偱偁傞丅 丂偙偺乽亙尒偊亜愭峴愴棯乿偲偄偆偺傪乮傛偔夝傜側偄偺偩偑乯梫栺偡傞丅傑偢丄懠幰偵偮偄偰亙怱忣棟夝亜偡傞乮椺偊偽乭庡恖岞偺婥帩偪乭傪棟夝偡傞乯偵偼丄帺暘乮撉幰乯偑偦偺懠幰乮乭庡恖岞乭乯偲摨偠亙怱忣亜傪帩偰傟偽傛偄乮摨偠亙怱忣亜傪帩偰側偄帪偵偼丄怺偄棟夝偱偼側偄偲尵傢傟偰偟傑偆偩傠偆乯丅 偟偐偟丄捈愙揑偵懠幰偺亙怱忣亜傪抦妎偡傞庤抜偼側偄乮暥妛嶌昳偱偼彂偐傟偰偄側偄偙偲偑懡偄偟丄彂偐傟偰偄傟偽偡偖傢偐傞乮丠乯偼偢乯丅偦偙偱帺暘乮撉幰乯偑懠幰乮乭庡恖岞乭乯偲偍側偠亙怱忣亜傪姶偠傞乮偮偔傞乯偨傔偵丄懠幰偑壗傪尒丄壗傪暦偒丄壗偵怗傝乮姶偠乯乧乧偰偄傞偐傪峫偊丄帺暘傪偦偺棫応偵偍偄偰憐憸偡傞乧乧丄偲偄偆傛偆側偙偲傜偟偄丅偦偺庡挘偺摉斲偼杮彂傪撉傫偱丄奺恖偱敾抐偟偰梸偟偄偲巚偆丅 乮1991擭02寧乯 搶戝弌斉夛 擣抦壢妛慖彂侾 1985 |