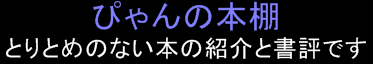
|
|
村上春樹編 『アンダーグラウンド』
この本は、著者・村上春樹が〈地下鉄サリン事件〉の被害者や被害者家族と直接会って話を聞き、そのやりとりをまとめたノンフィクションである。
巻頭、この本をまとめるきっかけが書かれている。それは、雑誌で読んだ被害者家族の投稿で、著者は、そのときは「手紙を読んで私はびっくり」するが「ため息をついて雑誌のページを閉じ、自分自身のいつもの生活と仕事の中に戻って」いく。 しかし、「そのあと、何かにつけてその手紙のことを思い出」すことになる。著者を去らなかった疑問はこう書かれている。 不運にもサリン事件に遭遇した純粋な「被害者」が、事件そのものによる痛みだけでは足りず、何故そのような酷い「二次災害」まで(それは言い換えれば、私たちのまわりのどこにでもある平常な社会が生み出す暴力だ)受けなくてはならないのか? まわりの誰にもそれを止めることはできなかったのか? そして、この「二種類の暴力」について「それらは目に見えるかたちこそ違え、同じ地下の根っこから生えてきている同質のものである」と思いはじめ、著者は、被害者たちのことを知りたいと思うようになる。著者・村上春樹の気持ちは次の一文に集約されているように思う。 個人的に。 この四文字で一文。わざわざ一文にするだけの重みがあったのだ。この一文に続けて、著者は書く。 そしてかくのごとき二重の激しい傷を生み出す我々の社会の成り立ちについて、より深い事実を知りたいと思うようになった。 ◇ この本のつくられ方について、著者・村上春樹は12頁にわたって説明している。 一年間をかけて、62人にインタビューしたこと。 著者自身が直接会い、1時間半から2時間(場合によっては4時間)にわたって話を聞いたこと。 録音をテープ起こしし、著者が文章を整え、インタビュイー(インタビューを受けた人のこと)にチェックを受けて削除・修正し(最大限、インタビュイーの意向を反映)、最終的に同意が得られた場合のみ掲載したこと(結果、掲載は60名)。 などなど。 印象的だったのは、証言者の探し方だ。著者とリサーチャー、編集者は話し合った末、困難な道を選択する。 本書のために進んで証言して下さる被害者の方を、マスコミ媒体を通じて一般に募るという方法もあった。「私はこのような本を書いております。つきましてはお話を聞かせてください」と。そうすれば結果的に、もっと数多くの証言を拾うことはできただろうと思う。実際に、取材がどこかで息詰まるたびに、それをやってみたいという誘惑にかられたのだが、リサーチャー及び編集者と何度か協議して、最終的にその方法は以下の理由で避けることにした。 ◇ 証言(もちろん、村上春樹が読みやすくまとめたものだが)を読んでいくと、人間の言葉を聞いているように感じる。これは、そうなるように「個人的な背景の取材に多くの時間と部分を割い」て話を聞き、そうなるように書いた成果なのだが、マスメディアを通じて作り上げる被害者のイメージとは異なる。著者はこんなふうに説明している。 そのような姿勢で取材したのは、「加害者=オウム関係者」の一人ひとりのプロフィールがマスコミの取材などにって細部まで明確にされ、一種魅惑的な情報や物語として世間にあまねく伝搬されたのに対して、もう一方の「被害者=一般市民」のプロフィールの扱いが、まるでとってつけたみたいだったからである。そこにあるのはほとんどの場合ただの与えられた役割(「通行人A」)であり、人が耳を傾けたくなるような物語が提供されることはきわめて稀であった。そしてそれらの数少ない物語も、パターン化された文脈上でしか語られなかった。 この部分を引用すると、村上春樹がマスコミを否定しているような印象を与えるかもしれないが、そういうことではない。そうなってしまう原因もその役割も著者は理解している。その上で村上春樹は「できることなら、その固定された図式を外したいと思った」のだ。 ◇ 60人の証言を読んで感じたのは、1945年に原爆を投下された広島の被害者(被爆者)の体験談(1965刊行『原爆体験記』広島市原爆体験記刊行会編)と似ていることだった。もちろん、まったく異なる体験であり、時代も違う。にもかかわらず、その言葉が伝えてくるものが似ていると感じた。 あまりにも大きな殺意。 しかも、個人としての自分が狙われたのではなく、不特定多数を狙った攻撃。 怒りが表に出てこない。怒りの感情がないのではなく、表に出てこない。理不尽な経験による怒りは静かに結晶しているように感じる。 原爆の被害者に対する世間の差別。 サリン事件の被害者が受けた二次災害。 原発事故の被害者に対する世間の攻撃。 村上春樹が「同じ地下の根っこから生えてきている同質のもの」と書いた根っこは、古くから、世間(日本社会)つまり私たちの中にあるのだろうと思う。 ◇ 巻末で、著者・村上春樹は再び、自分の思いを書いている。 人々はこの異様な事件にショックを受け、口々に言う、「なんという馬鹿なことをこいつらはしでかしたんだ。こんな狂気が大手を振って歩いているなんて、日本はいったいどうなってしまったんだ。警察は何をやっている。麻原彰晃は何があっても死刑だ」。 マスメディアが世間の圧倒的多数に逆らって流れをつくることはできない(できないことを村上春樹はよく知っているようで相乗作用として述べている)。言い換えれば、私たちが作らない限り、大きな流れはできない。 著者は、「こうした大きなコンセンサスの流れの果てに」、私たちが「どのような場所にたどり着いたのだろう?」と問う。そして「ひとつだけたしかなことがある。ちょっと不思議な『居心地の悪さ、後味の悪さ』があとに残ったということだ」と書いている。そして「私たちの多くはその「居心地の悪さ、後味の悪さ」を忘れるために、あの事件そのものを過去という長持ちの中にしまい込みにかかっているように見える」とも。 村上春樹は、「〈乗合馬車的コンセンサス〉の呪縛を解く」ために必要な「新しい言葉や物語」を探そうとする。 この地下鉄サリン事件の実相を理解するためには、事件を引き起こした「あちら側」の論理とシステムを徹底的に追求し分析するだけでは足りないのではないか。もちろんそれは大事で有益なことだが、それと同じ作業を、同時に「こちら側」の論理とシステムに対しても並行して行っていくことが必要なのではあるまいか、と。「あちら側」が突き出してきた謎を解明するための鍵は(あるいは鍵の一部は)、ひょっとして「こちら側」のエリアの地面の下に隠されているのではあるまいか? 字面で見ると、ありがちな"キレイゴト"を言っているようにも読めるが、著者にとっては深く刺さったものらしい。巻末の文章をすべて読むとそれが伝わってくる。少なくとも、村上春樹は自分のこととして考えている。 オウム真理教という教団の存在を知ったのは、それが最初だった。そのような選挙キャンペーンを見たとき、思わず目をそらせてしまった。それは私がもっとも見たくないもののひとつだったからだ。……(中略)……。私がそこでまず感じたのは、名状しがたい嫌悪感であり、理解を超えた不気味さであった。……(略)。 こうした問い直しに対して、ならば彼らを赦すのかといった反発を感じる人もいるだろう。もちろん、著者はそんなことを言っているわけではない。ただ、そうした反発を感じる人は、なぜ反発を感じるのか、その理由を立ち止まって考えてみる必要があると、村上春樹は言いたいのだろうと思う。 ……(略)……、私は実はこう思っている。「こちら側」=一般市民の論理とシステムと、「あちら側」=オウム真理教の論理とシステムとは、一種の合わせ鏡的な像を共有していたのではないかと。……(略)……。 ◇ 著者が「譲渡された自我、与えられた物語」と題して書いている部分が、「もうすこし詳しく説明させていただきたい」といった中身である。この部分を読みながら、2017年の地球(とうぜん日本も地球の一部)に起きている規模の大きな事件や規模の小さなトラブルの地下にも共通に存在するものを、村上春樹が語っているように感じた。それが何かは、ぜひとも実際に読んで欲しいと思う。 (2017年03月・筆) 講談社 1997刊 |