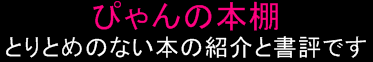
|
|
佐伯胖・佐々木正人編 『アクティブ・マインド 人間は動きのなかで考える』「人は考えるから動くのではなく動くから考えるのだ」これが、本の腰巻に書かれているキャッチコピーである。 人間は「まさに、『動いている』なかで『考えて』おり、『考える』ことがそのまま同時に『動くこと』になっている」という観点から、「人間がつねに動き回り、外界に働きかけることによって認識をつくりだし、修正し、そして外界について、より確かな情報を抽出している、ということをなんとかして浮き彫りにしようと」した本である(本書はしがきより)。 扱われているのは、 視覚 スリップ 姿勢 感情(表情フィードバック) 記憶(フラッシュバルブメモリー) カテゴリー 音声と文字 「読む」こと 推論と活動の文脈(保存課題の再考) である。 各章はそれぞれに話がまとまっているので、興味のあるところだけを読むのもよいだろう。 認知科学は難しくて、それぞれの内容を簡潔に紹介するのは手に余る。が、この本が面白く、読む価値があることは保証できる。 それも単に研究・理論として面白いだけでなくて、実生活を見直すのに(うまく使えて)役立つと思う。 スリップを例に挙げよう。スリップというのは「一般に、意図しなかった行為を遂行してしまう誤り」のことで、それも「普通なら容易にできるような、本人にとってやり慣れた行為が、なんらかの原因で、たとえば『うっかり』と、失敗してしまう」のである。 こうしたことは日常生活でもよくある。たとえば、学校生活でよくあるのが、漢字の書取りの宿題で同じ漢字を何回も練習するとその中に字を間違えて書いてしまうような場合である(「類」の字を書くつもりが「数」と書いてしまったなんて記憶は誰にもあるでしょう)。 これは急速反復書字(実験的にスリップを誘導する方法)にあたる。つまりできるだけ速くたくさん同じ字を書こうとする(漢字の書取りなんて早く終りたいもんね)と、身体が意図に逆らって動いてしまうのである。本書によると大学生でも被験者の約半数(「お」を50回書く場合)がスリップするそうだ。 そして「わかっていてもスリップは抑制できない」。書字の場合、過剰熟練行為である(ひらがなや「類」「大」の字なんかの場合)とスリップするらしい。そりゃそうでしょう。憂鬱の「鬱」の字なんかお手本を見ながらか、いちいち考えながらじゃなきゃ書けないからスリップしそうもないもの。見たこともない「歙」(キュウ、すう:吸う、息をすいこむ)や「饑」(キ、うえる:飢えるに同じ)なんかだったらなおさらだ。 ちょっと話を変えてこれを学校場面で考えると、小学生なんかの漢字の書取りの間違えがスリップだったら別に指導しなくてもいいわけで(指導しても無駄でしょう、わかってても抑制できないんだから)、それをもし不真面目だから間違うんだみたいに言ったらやる気がなくなってしまうでしょうね。 逆にスリップでない(ミステイク)なら、これはきちんと指導しなくちゃいけない。(ノーマンは人間のエラーをスリップとミステイクに2大別しているそうだ。後者は行為の最終的な目標を適切に形成することができなかった場合である。つまり「類」と書くべき課題にたいして、「数」と書こうと考えて「数」を書いた場合である。他方前者は「類」と書くつもりなのに身体が勝手に「数」と書いてしまう場合である。) これ以外にも、音声と文字の章(7章)や「読む」ことを扱った章(8章)はかなり教育的な場面への示唆を含んでいると思います。誰であれ、読んで損はありません。 (1990年09月) 東大出版会 1990刊 |