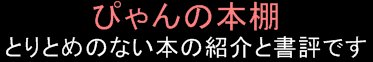
|
|
『この身近な危機 レイプ・クライシス』まえがきによるとこの本は東京・強姦救済センターというボランティア団体が1989年 2月17日から 3月24日まで毎週1回、6回連続で開いた連続講座の内容を5回にまとめたものです。この団体は「強姦や性暴力の被害者の女性のための電話相談を主な活動とし、併せて強姦を容認し助長するものへの告発活動をして」います。その基本的な前提は、まず「女性が望まない性行為はすべて強姦」であるということと、強姦の被害者には何ら責任はないということです。 では、この本の内容をごく簡単に紹介しましょう。 まず第1回「ポルノは女への暴力だ」ではポルノとエロスの違いがテーマとなります。 そこを引用すると「私たちはポルノとエロティックなものを区別します。私たちがポルノと呼ぶものは女が乱暴されたり、殺されたりする暴力的で一方的なもので、エロティックとは、生命を肯定し生きる活力を与えるものであり、互いが分かち合うもので」あるとされています。また「ポルノが暴力的なのは、女が殴られたり殺されたりすることだけを指しているのではありません。ポルノとは、男が女の身体を自分たちの快楽のために“もの”として扱うことです」という表現もあります。 つづいて、ポルノというジャンルが実際どのようなものを含むのか、様々なメディアの実際が紹介されています。具体的にはSM写真やSM映画、レコードジャケット、マンガ、ビニ本、宣伝ポスター、雑誌、雑誌の表紙などです。なかには一見ポルノではないと思われるもの(宣伝ポスターはJALのもの)もありますが、そこに共通して存在する女性をおとしめるイメージ(それが意図されたものであれ意図されないものであれ)が問題とされているわけです。ポルノのなかでの歪められた女性のイメージや様々な誤ったメッセージ(例えば、「女性は襲われ、抵抗するが、結局は受け入れ楽しみさえする」など)が与える影響をもっと認識して、それに対して反対の声を上げなくてはならないことを言っているわけです。このあたりのことを一言で言い表すと「ポルノは理論で、強姦はその実践」ということになるでしょう。 第2回「女性にとって性的自由・自立とは」では、<性の自己決定権>と<性的自立>がテーマとなります。 自己決定権とは何か? ひとつは「プライバシーの権利の一つの側面」であり、もうひとつのより重要な側面は「ある種の個人に関わる決定をするにあたって、その個人が独立性をもっているという、そういうことの利益だということ。つまり、他人に関係ないことや他人に害を及ぼさないことについては、その人の決定が最高のものであるという考え方」なのだそうです。そしてこれが性の問題を考えるうえで重要であることが述べられ、いくつかの観点から考察されています。観点としては強姦罪・性的いやがらせ(いわゆるセクハラ)・買売春・中絶と堕胎罪・有責配偶者からの離婚請求・夫または妻から相手の愛人への慰謝料請求がとり上げられています。 すべてをくわしく紹介することはできませんので、強姦罪という観点について簡単に言うと、ここでは<性のダブル・スタンダード>が扱われています。具体的には強姦罪というものが、1990年現在、法律のなかでどういうものとして解釈され扱われているのかが書いてあるのだが、ここでショッキングなのは強姦罪が女性を保護するというより社会的な秩序とか性風俗(公序良俗)を守るためのものだということである。つまり、守ろうとしているのは女性の権利(自己決定権)ではなく「女の貞操」だということである。それが具体的には以下のような事実に反映していることが述べられる。強姦罪の構成要件にある暴行・脅迫がただの暴行・脅迫では駄目だとか、被害者に暗黙の承認があったら強姦罪にならないとか、女性が「ノー」と言っても拒否を表したことにならないと(裁判所も)考えるとか(「助けて」と言えばいいみたい)、妻には性行為に応じる義務があるのだから夫が妻の意志に反してやっても強姦罪にならないとか、被害者に落ち度(不注意)があると見做されると加害者が無罪になりやすい(少なくとも軽くなる)など、ちょっと信じられないような事実にである。 第3回「つぶせ! 強姦神話」では、第1回、第2回にも登場する強姦神話をとりあげ、それがどういう内容をもちどう誤っているかが述べられます。主な強姦神話として紹介されているものを引用します。 (1) 強姦されるのは被害者に責任(落ち度、軽率、挑発)があるからだ (2) 本当に嫌だったら最後まで抵抗できるはずである (3) 強姦するのは見知らぬ男である(顔見知りの間では強姦にならない) (4) 女性には、強姦願望がある (5) 普通の男は強姦などしない。強姦は特殊な男の犯行である (6) 性的欲求不満が強姦の原因である では、実態はどうなのか。これも引用しましょう。 (1) 被害にあった理由はただひとつ、それは被害者が「女」だったからです (2) 被害者が抵抗しきれないのは、体力の差があることと、殺されるかもしれないという恐怖のせいです (3) 加害者と被害者は、顔見知りである場合がずっと多い(見知らぬ人間による被害が無いという意味ではありません) (4) 女性は、罪悪感を持たなくてすむため、強制されるような性行為を空想することがありますが、実際に強姦されることを望んでいるのでは決してありません (5) 加害者のほとんどは、普通の生活をしている男です (6) 性的欲求不満は原因のひとつでしかなく、社会的欲求不満のはけ口や、女を征服して男らしさを確認したい欲求から犯行に及ぶ場合が多い この回でも第2回と同様、強姦罪がとり上げられて(議論の内容も重なっている部分もある)いますが、ここでは具体的な判例(つまり現実の司法の判断)についてのケーススタディがなされます。このなかには、被害者に暗黙の承認があったと加害者が誤解するのももっともだとされる理由を認め無罪になった判例もあります。あと量刑がかなり軽い傾向があるということも紹介されていますが、司法のセンスと世の中の常識的な感覚との隔絶はちょっとひどすぎる感じです(強姦罪で執行猶予がつく率は33.6%、量刑では3年以下が81%)。 第4回「ハードでもソフトでもレイプはレイプ」では、顔見知りの男によるレイプの形態として<デートレイプ>というものがテーマになっている。ここではアメリカでの事例をケースとしてケーススタディし、A(被害者の立場)、B(被害者の友人)、C(加害者の恋人)の3グループに受講者を分けてグループワークをさせて意見を発表させているのが記録されています。そしてそれらの意見をもとにセンターの方から説明があるわけです。ここで扱われているような事例に対する普通の反応は、被害者に責任があるのだから自業自得だというもので、多くの人が強姦神話によって正当化することが紹介されています。 また、デートレイプが生じてしまう根のひとつとして、<女のNO、女のYES>という問題が論じられてもいます。さらに根本的な根として登場してくるのが<性差別と強制異性愛>というものです。異性愛そのものは「男と女は愛し合うものだ」と綺麗なんだが、そこに性差別が入ると「女は男を愛するものだ」という形で女性に強制がかかるようになる。それが<強制異性愛>だというわけです(男は女を愛するものだという逆向きのベクトルがない)。こうした議論の流れのなかで「女性の性的自由、自立の第一歩というのは、まず男に嫌われてもいいと思うことから始まるのではないか」ということがでてきます。 最後の第5回「女の身体をとり戻そう」では、女性の身体についての社会的な偏見(産む性と娼婦の性の二つに社会イコール男によって規定されてしまうことなど)があつかわれています。そして、からだの自己決定権が論じられています。 全体をまとめれば要するに、レイプを巡って現在存在する問題(はっきり言ってスゴイんです、これが)がどういうものであり、これからどうなっていくべきかを考えようとしている本です。これくらにのことは基本としてすべての人間が知っているべきではないでしょうか。是非、読んで欲しいと(特に男性に)思います。 (1990年10月) 学陽書房 1990 こんな本も 『レイプ・男たちからの発言』 『レイプ神話解体新書』 |