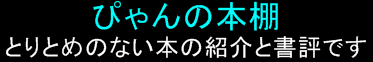
|
|
中村真一郎編 『ポケットアンソロジー 恋愛について』自慢にもならないことなのですが、恋愛を扱った作品はあまり読んでいません。あるいは、恋愛を扱った作品でも恋愛という視点からは見ないと言ったほうが良いかもしれない。とにかく、恋愛物と意識して恋愛物を読むことはほとんどなかった。これは、「恋愛」という代物にたいして極めて懐疑的だということも関係があるのかもしれないですね。人間は通常、自分の経験を物事の判断の基準として使うでしょう。他に基準が持てれば別ですが、それがなければ自分の経験を使うしかないわけですから。自分の経験から考えて「恋愛」について非常に懐疑的なわけです。私は極めて(と言っていいのだろうと思いますが)惚れっぽい人です。そして同時に極めて(と言いきっていいでしょう)さめやすい人です。とにかく「恋愛感情」(なのかしら)が長続きしない。簡単に言ってしまえば、すぐ誰かを好きになるくせに一週間もするとその人への特別な感情が消えてしまうのです。その人が嫌いになるとかそういうことではないのだけれど、特別な感情(果たして「恋愛感情」と呼べるのだろうか)は消滅してしまう。つきあいが長続きしないという人は結構世の中に居るみたいですが、それ以前の段階で長続きしないわけです。こんな経験ばかりしていると「恋愛感情」というのは長続きしないものだろうと判断するようになるわけで「一週間ようすを見ていればさめるだろう」と思ってしまう一方で、「どうして他人は恋愛感情が長続きするのだろう? 本当に続いているのだろうか?」なんて思うわけです。こういう背景を持っているのですが、この本を見かけた時にちょっと読んでみようかなと思ったわけです。 余談が長くなってしまいました。この本の紹介をしましょう。アンソロジーというのは詩文などの選集のことで、この本は<恋愛>についての様々な文章を集めているのです。選ばれている筆者は以下の通りです(掲載順)。 森瑶子 富岡多恵子 大庭みな子 倉橋由美子 瀬戸内寂聴 谷川俊太郎 遠藤周作 吉行淳之介 梅原猛 作田啓一 福永武彦 中村真一郎 椎名麟三 武田泰淳 円地文子 伊藤整 太宰治 坂口安吾 石川淳 全体の印象としては、女性の文章がわりと具体的というか、恋愛なり結婚なりについて足が地についた感じで書かれているのに対し、男性の方が論文ぽい感じで読んでいて嘘っぽくてつまらなかった。これは、筆者の責任もあるのかもしれないけれどアンソロジーの場合、編者のセンスの問題が大きいと思います。 これらの中から面白かった物を挙げれば、男性では太宰治、女性では倉橋由美子。 太宰のも倉橋のも彼自身彼女自身の経験に関わる文章です。太宰のは『チャンス』で、この中で彼は自らの経験から「恋愛は、チャンスではないと思う。私はそれを意志だと思う」と言っています。主張について賛成するのも反対するのも読む者の自由でしょうが、面白いことだけは確かです。しかし、太宰以外の男性の文章が面白くなかったのは何故だろう? さて、倉橋のは『愛と結婚に関する六つの手紙』で、彼女がかつて男友達に書いた手紙を六つ(適当な加工は加えた上で)紹介しています。彼女は結婚の申込に対してすべて《non》を言っており、その調子もその時、その相手によっていろいろです。特に17歳の時の手紙(結局出さなかったと書いてありますが)の罵倒の激しさはちょっと凄いものがありました。倉橋が自分で書いているように「あなたがまだ若くて、結婚をそれほど身近に感じていらっしゃらないとすれば、『あたし、一生お嫁にいかないわ』と宣言していた少女(中略)が大きくなってもなおその考えをもちつづけていることに、多少の興味をおぼえられるでしょう」というわけです。倉橋由美子のこの文章は4番目に並んでいるのですが、種を明せばこの倉橋さんの文章が半月の間、恋愛物とつきあうきっかけになったのでした。でも、この倉橋さんのは本当におもしろいですよ。これと太宰治の二つだけで十分、値段分の価値はあります。 (1990年08月) 岩波書店文庫 1989刊 |