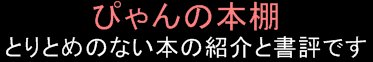
|
|
筒井康隆著 『短篇小説講義』この本は筒井流短編小説論で、古典といえる短編小説をとりあげて論を進めている。そのおおもとにある認識は「小説というものは、いうまでもなく、何を、どのように書いてもいい自由な文学形式な」のに、何故か「模範的な短篇小説が存在するという観念の一般化があ」るということだ。著者は、この観念の一般化は「短篇小説を書く上での規範があるということ」を意味し、それはおかしいと言う。そして次の様な問をたてる。「それならなぜ今、小説作法の類の書物や、発言や常識と称されるものや、コツと称されるものや、その他何やかやが巷間に満ちているのだろう。そしてそれらの中には特に、短篇小説を対象にしたものが多いように思われるのだが、これは何故だろう」。 この問に対しての解答は本書を読んでもらうとして話を進めよう。 筒井氏は(短篇)小説は自由な文学形式だということから、「短篇小説という形式の外在律は、短いということだけだろう」という。そして続いて短篇小説の「内在律」が論じられる。ここから本書が扱う重要な問が生じる。 「まだ近代小説というジャンルが確立されて間なしの、もちろん短篇小説作法などというものも存在しない時代、作家たちが短篇小説を書く上で内在律としていたものは何だったのだろう。現代にまで至っている短篇小説と言うものの形式を彼らに創造させ、確立させた内在律とはどんなものであったのだろう。……他の文芸ジャンル……詩とか戯曲とか……そうした既製のジャンルの方法論、あるいは絵画や音楽といった他の芸術ジャンルの方法論、または……自然科学の方法論の影響などを受けていたのだろうか。それともその時代、彼らはそもそも内在律などというものを持たず、まったく自由に短篇小説の方法を無から創造していったのだろうか」。 これらの問題に答えるために筒井氏はその時代に書かれた短篇小説を虚心に読み返した。そして、こうした作業から「初読のものの中には現今のいわゆる短篇小説作法の枠からは大きくはずれたものがたくさんあることを発見」する。この本は、そうした「短編小説の作者に、それぞれの作法でこれらの作品を書かせた内在律とはいったい何だったのか」「短篇小説というジャンルが確立されたのちにおいても、それぞれの時代に、それぞれの手法で書いた作家は、短篇小説にどのような創作態度でのぞんでいたのか」という問を、そうした短篇小説のうち7つの短篇と一人の作家を紹介しつつ、考えていく(以上、1章を簡単に要約)。 紹介されるのは『ジョージ・シルヴァーマンの釈明』(ディケンズ)、『隅の窓』(ホフマン)、『アウル・クリーク橋の一事件』(アンブロウズ・ビアス)、『頭突き羊の物語』(マーク・トウェイン)、『二十六人の男と一人の少女』(ゴーリキー)、『幻滅』(トオマス・マン)、サマセット・モームの短篇小説観、『爆弾犬』(ローソン)。 (1990年10月) 岩波書店 新書 1990 |